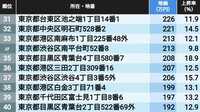「コハウジング」を選択する人が増えている理由、コミュニティー意識が高まるものの共同生活ならではの難しさも
プロジェクト候補は持続可能性やイノベーション、そして中間層が価格高騰で排除されるのを防ぐため、相場以下の家賃を提供できるかどうかといった観点から評価される。チューリヒ市内の賃貸物件の空室率はわずか0.07%となっており、スイス政府が不足と見なす1%の水準を大きく下回っている。だが、協同組合や市営の5万5000戸の住宅は、民営と比べて約25%安い。

コハウジングは欧州だけでなく、オーストラリアやニュージーランド、米国などにも広がりつつある。ニューイングランドや太平洋岸北西部などでプロジェクトが立ち上がっているが、米国での拡大ペースは鈍い。米国人は住宅を主要な運用資産と見なす傾向にあるためだ。
これに対し、コハウジングの仕組みでは、住民は物件を賃貸するか、協同組合の持ち分を購入し、退去時にはほぼ利益を得ることなくそれを売却するのが一般的だ。
もう一つの課題は、米国では住宅支援が主に低所得者を対象としているのに対し、欧州諸国ではより幅広いアプローチが採用されている点だ。ハーバード大学住宅研究共同センターのリサーチフェロー、スザンヌ・シンドラー氏は「チューリヒには協同組合住宅に住んでいる富裕層さえいる」と話す。
共同生活
チューリヒ市で住宅政策を担当するフィリップ・コッホ氏は、同市のようにコハウジングが盛んな都市でも、住宅市場全体に占めるコハウジングの割合は今後も比較的小さなものにとどまると指摘する。
関心は高まっているものの、共同生活に適応するのは容易ではなく、従来型のアパートに比べて住民の入れ替わりも多くなるといい、「応募者の多くは実際にどんな生活が待っているか十分理解できていない」とコッホ氏は語る。
コハウジングの利点の一つは、人口密度の高い都市において1人当たりの居住面積を減らせることだが、「この違いだけで住宅不足が解消されるわけではない」とコッホ氏は言う。実際には、より多くの面積を必要とすることさえある。