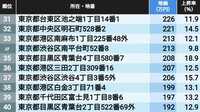「コハウジング」を選択する人が増えている理由、コミュニティー意識が高まるものの共同生活ならではの難しさも
世界でこうしたコハウジング形態を選択する人が増えている。テンペルリさんの住まいは「クラスターフラット」と呼ばれ、親類ではない人々と住宅を共有する。これらは学生や社会に出たばかりの若者でにぎわう寮ではなく、8人、10人、12人、あるいはそれ以上の居住者向けの物件であり、単身者や家族、高齢者などの間で人気が高まっている。
コハウジングの概念は、自由な発想が広がった1960-70年代の北欧デンマークで生まれたと指摘されることが多い。当時、共同生活への願望から共有を目的とした住宅を建設する動きが広がった。その後、他の欧州諸国にも拡大し、不動産の専門家によれば、チューリヒはこうした流れで先行する都市の一つとされている。
「20年余り前に最初のクラスターアパートを建てたときは、正気ではない、入居者は集まらないと周囲から見られていた」。チューリヒで4つのプロジェクトを持つ協同組合クラフトベルク1のマネジングディレクター、アンドレアス・エングバイラー氏はそう振り返る。「それが今では主流になりつつある」と語る。
通常、各居住者に専用バスルームとプライベートスペースを提供するクラスターフラットの多くを運営しているのが住宅協同組合だ。例えば、協同組合のメア・アルス・ボーネンは、各7-12人が住むクラスターフラットを設けており、それが11戸ある。
こうした協同組合はリビングスペースに加え、屋上庭園、電動工具やミシンを備えた作業室、音楽練習室、ホテルのような宿泊用ゲストルームなどの共用エリアを用意していることが多い。メア・アルス・ボーネンの住民は自家用車の所有を制限されているが、共有自動車の利用は認められている。
ドイツ連邦建築研究所による2018年の調査では、同国やオーストリア、スイスで数十のクラスターフラット・プロジェクトがあることが分かったが、こうした市場に関する統計を正確に把握するのは難しい。そもそもコハウジングが何を指すのか定義自体が曖昧だ。
暮らしを楽に
しかし、生活費を抑えたり、コミュニティー意識を望んだりする人が増える中、コハウジングを求める傾向は強まっていると、不動産の専門家らは指摘する。コハウジングの住民は食事や掃除を共同で行ったり、夜や週末を一緒に過ごしたり、パーティーを開いたりすることも多い。
シュツットガルトで国際建築展の責任者を務める建築家、アンドレアス・ホーファー氏は「今や住宅開発提案の多くにクラスターフラットの要素が求められている」と明かす。