もう1つの重要な業務が、資金ギャップの調整です。銀行では日々の預金業務や貸出業務で、多くの資金が必要になるのはいうまでもありません。にもかかわらず、もし資金が足りないようなことになれば業務が滞ってしまうため、資金を市場で調達するなどの調整を行う必要があるわけです。
その市場には短期金融市場と長期金融市場があり、前者はマネーマーケットと呼ばれ、銀行や証券会社など金融機関だけが取引できるインターバンク市場と、一般の企業も参加できるオープン市場があります。
長期金融市場はキャピタルマーケットとも呼ばれていますが、その代表が株式市場と債券市場です。銀行は資金が足りなくなりそうになると、こうしたさまざまな市場から調達しているわけです。
特にインターバンク市場は銀行にとって預金に次ぐ資金の仕入先ともいえ、日本では「無担保コール翌日物」という取引が主体になっています。当然、資金を借りる際には利息が発生しますが、その際に適用される金利が「無担保コールレート(翌日物)」であり、現在の日本の政策金利に位置づけられています。
資金の調達のほか、貸し出しや運用も
逆に資金に余裕があれば、他の金融機関に貸し出したりもしていますし、また、資金の調整というよりは、収益を獲得するために資金を運用したりもしています。
運用対象は国債や地方債、社債、株式、投資信託などさまざまですが、いずれも利息や配当金などの獲得を目的にした中長期運用が中心となります。
それに対して前述のディーリング業務では、短期の売買による収益の獲得を目指しているため、同じ証券部門が行う運用でも性質はかなり異なります。
そのほかにも、証券部門では経済や市場動向の調査、分析を行い、その結果を窓販業務の関連部署や支店などに発信したり、投資信託などの新商品を導入する際にアドバイスをしたりする場合もあります。
さらには、顧客向けのリポートを発行したりしているケースもあり、銀行の中でも高い専門性を求められる部門といっていいでしょう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

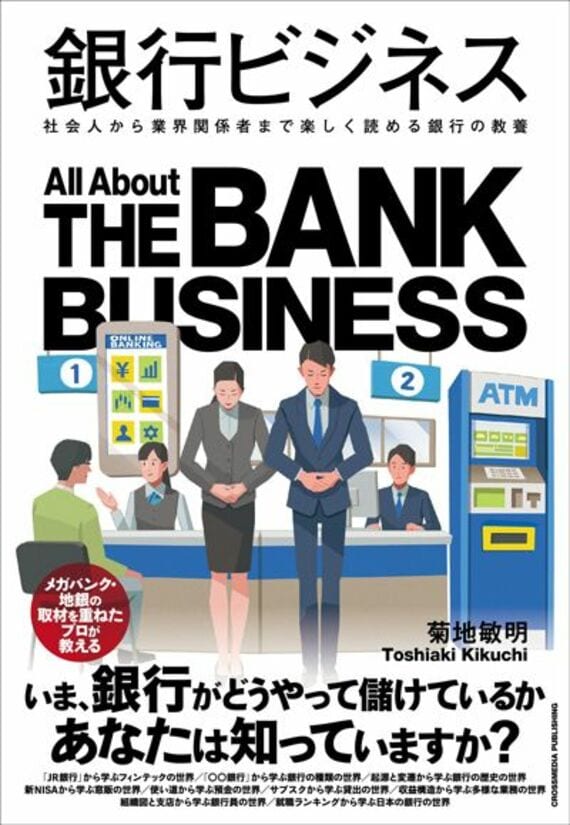
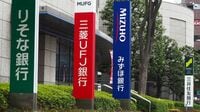





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら