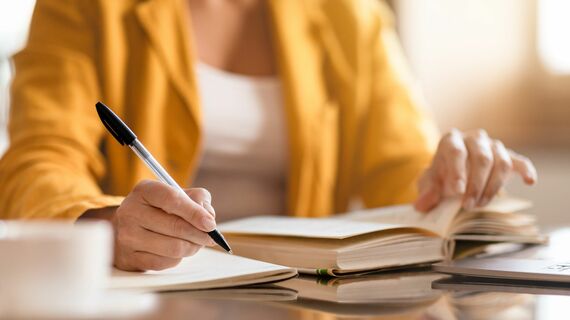
脳のメモ帳「ワーキングメモリ」とは?
誰もが、日常会話で使う「生活言語」と教科書で使われる「学習言語」とのギャップに、戸惑った経験があるのではないでしょうか。
私自身も大学で論文を読み始めたとき、その難解な専門用語や構文に苦労し、輪読や議論を通じて少しずつ慣れていきました。
中高生で出会う数学の証明の文章も、『シン読解力』を読んで「数学語」だったのだと感じました。
私が学生のときにも、公式が理解できない、計算ができないのではなく、「ゆえに」「すなわち」などの独特な表現につまずいてしまう子が周りにいました。
数学に苦手意識を持ってしまうタイミングですよね。
これこそシン読解力に関わる「読み解く力」なのかと思います。
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら