あのドラッカーも驚いたという日本の人材育成法…その根底には100年変わらない"老舗の流儀"がある
そして、「手を抜かずにやり遂げたときに感じる喜び」を心と体で実感させることを最優先にします。こうした経験の積み重ねが、手抜きのない誠実な仕事を実現させ、揺るぎない精神と、それに伴う技術を身につけさせていくのです。
答えを「外」に求めるのではなく「心の声」を聞く
昨今、業務効率化やミス防止などを目的に、業務手順やルールのマニュアルを作成する企業は少なくありません。しかし、越後湯沢にある1075年創業の老舗旅館「高半」は、マニュアルに頼らない人材育成を行います。
第36代女将・高橋はるみさんはこう言います。
「目の前にいるお客様に、どう接すればよいか。それをマニュアルのような『自分の外』に求めてしまったら、すぐ限界がきます。お客様の立場になってみたら、どうしてほしいか。それを『自分の心』に聞いてみる。その答えにしたがってみればいいと思うんです」
正解はマニュアルにあるのではなく、自分の心の中にある――、そのことに気づかせることが教育だというのです。
正しい行動とは、上司の指示や手順書のとおりに機械的に動くことではない。「いま、この状況で、自分は何をすべきか」と自問し、自らの良心の声にしたがって行動できる。それができたら、正解だというのです。そのため、マニュアルは「あえて作らない」と女将はいいます。
従業員が接客に際し、判断に迷うような場面で、女将はこう問いかけるのだそうです。「どうしたらいいと思う? あなたなら、どうする?」。 そして、従業員からの回答には、どんな回答でも、こう返すのだそうです。「そう、それでいいのよ。わかってるじゃない」。
女将は「答えは自分の内にある」ことを実感させようとするのです。これにより、従業員は自分の判断で行動する自信が身についていき、指示待ちではなくなります。判断の基準を外に求めず、自らの「良心の声」に耳を傾ける。これが、心のこもった個別対応、すなわち「神対応」につながっていくのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

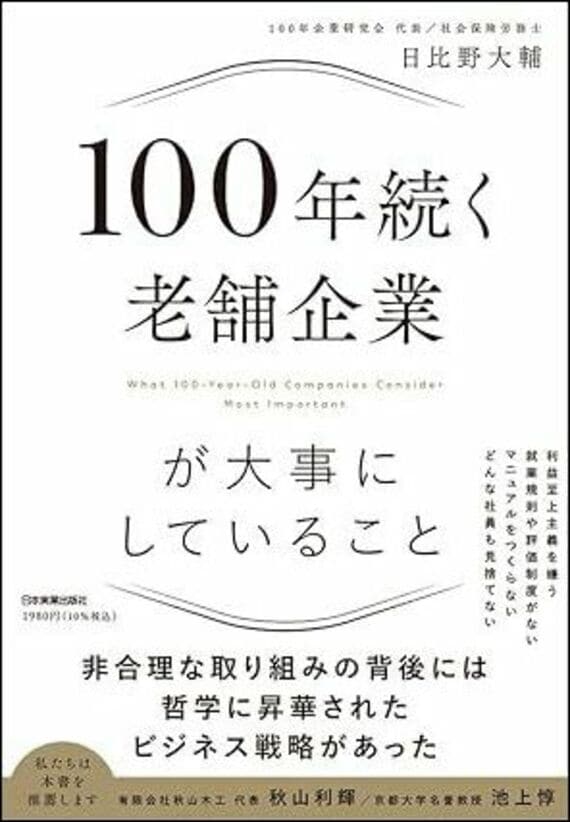






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら