中国・習近平への集権化に歯止め。四中全会で安全保障よりも経済重視と守勢に変わったが、再びの安保重視へ外敵に高市首相誕生の日本も利用か
高まる不満に、安全保障よりも経済重視に変わった習指導部。ただ、それは続くのか。注目は日中関係だ。
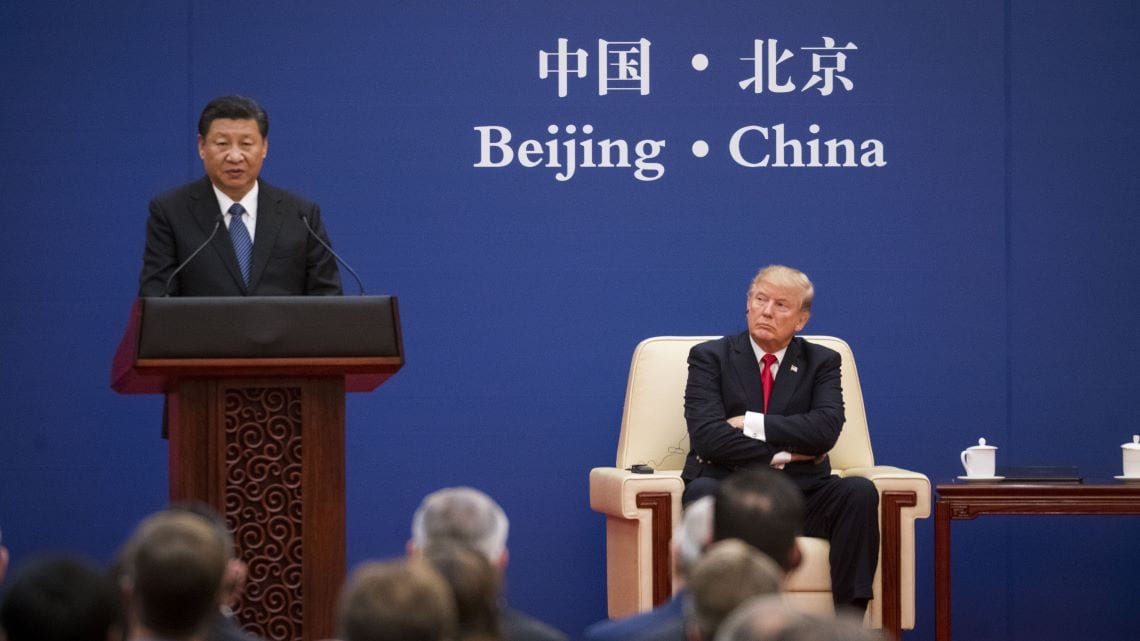
10月23日に中国共産党の第20期中央委員会第4回全体会議(四中全会)が閉幕した。今回、最も重要な議題は、2026年度に始まる第15次五カ年計画だった。多くの識者やメディアは「既定方針に変化なし」と報じたが、筆者の意見は異なる。この会議では習近平総書記の集権化に歯止めがかかり、中国経済の「ソ連化」のリスクが低減した。
「ソ連化」は、経済産業研究所の呉軍華氏がよく使う表現で、社会主義国が戦略産業に過大投資し、全体の経済均衡を歪めることを指す。習は中国の安全保障を懸念するあまり、長期的な対米闘争に有用とみられる戦略産業に国家資源を注入し、国有企業を優先してきた。国際関係の見通しの暗さは、総書記の任期を延長「せざるをえない」理由でもあった。
25年9月末の政治局会議は、習が唱える「ボトムライン思考」(最悪の一線に常に備えよとする考え)の強化を訴えた。しかし、四中全会のコミュニケはこれを消去。代わりに「実体経済の基盤を強化、拡大する」とし、民生重視や消費拡大を盛り込んだ。
国家発展改革委員会主任の鄭柵潔は四中全会会後の記者会見で、伝統産業は中国の製造業の80%を占めると述べ、中国は「実体経済に発展の重点を置き続ける」と強調。コミュニケ全体で安全保障の扱いはやや軽くなった。
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら