実は現在のお寺は、清貧どころの話ではありません。これからあと20年ほどの間に、現在7万件超ある仏教寺院のうち、3分の1から3分2ほどが淘汰されていくと私は予想しています。
江戸時代、お寺は幕府がつくった中央集権の仕組みの中で、管理されながらも安定した運営を行っていました。その中心となったのが、「本末制度」と「檀家制度(寺檀制度)」です。
「葬式仏教」と呼ばれるようになった理由
徳川家康は非常に賢く、お寺が幕府の脅威とならないように中央集権の仕組みをつくり、管理しました。各宗の本山(本寺)をトップとし、「本寺・中本寺・直末寺・孫末寺」のように上下関係がつくられました。例えば、私のいる愛知県にある福厳寺は、中本寺的な役割を担っていました。昔は福厳寺にも、修行僧がたくさんいたのです。
そして民衆は、各地域の末寺に所属することになりました。これが檀家制度です。末寺は人々の戸籍を管理しつつ、面倒をみたわけです。江戸幕府は寺を通じて、広く民衆を管理していたことになります。お寺にとっては、これが経済基盤の確保につながりました。「葬式仏教」などと揶揄されますが、お寺が葬式を担うようになったのは、亡くなった方を戸籍から抜くという実務的な作業が必要だったからです。
強制的な寺への所属が必要なくなった現在、檀家離れは急激なペースで進んでいます。江戸時代にあった広大な敷地や荘園は、明治の「上知令(あげちれい)」によりすでに失われています。現在のお寺は、非常に脆弱な経済基盤の上に運営されているのです。「坊主丸儲け」は遠い昔の話なのです。

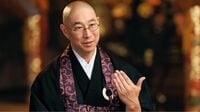
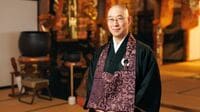




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら