この先、人々から信仰がさらに失われれば、お葬式や法事も縮小していくでしょうから、経済基盤の弱いお寺から順番に朽ちていくことになるでしょう。
現実的な面でいえば、お寺は普通の家とは違うので、「この扉を変えよう」といってホームセンターで買ってくるわけにはいきません。瓦(かわら)が使われている屋根の雨漏りの修繕に1000万円を用意しなければならないなど、維持するだけでも簡単ではありません。
さらに、いくらお金を用意しても、職人さんがいなくなれば、修繕をしてもらうことはできなくなります。「しっくい」を塗ってくれる職人さんも、建物の状況に合わせて材木を調整してくれる大工さんも本当に少なくなりました。これからはちょっとした修繕ひとつとっても、資金の面でも、職人さんの手配の面でもさらに難しくなるはずです。
人はストイックな姿勢に心を打たれる
私がこのように、お金の話をすると非常に嫌がる方がおられます。そういった方というのは、どうやら僧侶に「清貧であってほしい」と思われているようです。その気持ちもわからないではないのですが、実は仏教に清貧の思想はありません。
それはお釈迦様がつくられた修行の仕組みを見るとわかります。お釈迦さまは、ご自身や修行僧が修行に専念するために、「托鉢(たくはつ)」という仕組みを考え出しました。僧は修行に100%自分の時間を捧げるために、生産活動をしないと定めたのです。食事をつくることも、仕事をすることもしない。食べ物は、人々から恵んでいただくという方法です。

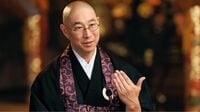
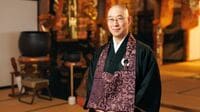




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら