これは現代にたとえると、オリンピック選手とサポーターの関係と似ています。選手は自分のすべての時間をその競技に費やす。スポンサーなどのサポーターは資金を出してそれを支援する。十分な支援があれば、選手は集中して競技に取り組み、高いレベルのパフォーマンスを披露することができます。私たちはその姿を見て、励まされ、元気づけられるのです。ストイックに競技に打ち込む姿に、心を打たれるわけです。
もしあなたがサポートしている選手が、SNSに「ベンツの最新型を買いました」「今日も高級焼肉です!」といった投稿を繰り返していたら、どう感じるでしょう。
「もっと練習しろよ」と思うかもしれません。応援したいという気持ちを失ってしまうかもしれません。たとえ選手にそのような金銭的な余裕があったとしても、サポートしてくれる人々に見せる姿はやはり「ストイックなアスリート」でなければならないのです。
現在のお寺は清貧どころではなく淘汰が迫る
托鉢によって皆さんからいただいた食べ物や薬で修行を支えてもらっていた修行僧も、現在のオリンピック選手と同じです。心の修行という、自分のしたいことだけに100%時間を費やすのであれば、贅沢をしてはなりません。
人々が応援したくなるような、お布施をしたくなるような僧でいなければなりません。お釈迦様が生きていた時代の僧は、食事は午前に1回。持つことを許されたのは、歯をきれいにするための爪楊枝と托鉢用の鉢、そして「糞掃衣(ふんぞうえ)」と呼ばれる死体をくるむことに使われるようなボロ布が3枚だけでした。その姿が、僧を「清貧」に見せたのであって、清貧であることを目指していたわけではないのです。
清貧に見えなければ、お布施が集まってこなかったのです。

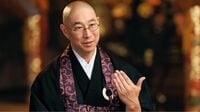
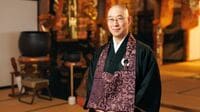




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら