「私と同じこと言ってるのに…」なぜあの人の言うことは聞いて、私だと言うことを聞かないのか?
2 肩書きと資格
大学教授や有名企業の役員など、社会的な地位が高い人の意見は重みが違う。元FBI捜査官のような特殊な経験を持つ人の発言にも、強い影響力がある。資格も同様だ。当社には税理士、公認会計士が多数存在するが、やはり資格があるかないかで、クライアント企業の社長の姿勢、態度は変わるようだ。
「立場がある=正しいことを言っている」という錯覚が、人の判断を左右してしまうのだ。
近年はSNSのインフルエンサーも権威性を発揮
3 メディアへの露出
テレビや新聞で取り上げられた商品は、たちまち信頼を得る。メディアに露出した専門家の言葉にも、大きな権威性を感じる。医師が「テレビでよく見かける先生」というだけで、その発言は重みを増すのだ。近年ではSNSのインフルエンサーも、「フォロワーが多い=影響力がある=信頼できる」という認識で、強い権威性を発揮するようになっている。
4 社会的な評価・認証
「国から認められている」「公的な機関が評価している」といった事実も、権威性を高める大きな要素だ。たとえば、特定保健用食品(トクホ)のマークや、モンドセレクション、グッドデザイン賞などの第三者評価は、多くの消費者に安心感を与える。
「みんなが認めている=自分も信じていい」という心理が働いている。
5 経歴の長さと実績
「この道30年」「1万人以上を指導してきた」といった数字も、人に強い印象を与える。たとえ内容に誤りがあったとしても、「長くやってきた人なんだから、正しいに違いない」と私たちは思い込みやすい。実績や経験年数は、それだけで説得力のある話し手という印象を作り出すのだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら















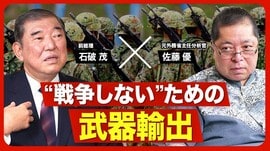















無料会員登録はこちら
ログインはこちら