こうして「東京生まれ東京育ち」の政治家や官僚が政界官界に入っていくわけですから、地方の生活や考え方、悩みの実情を「自分ごと」として捉えることは難しい。
自分たちの見える範囲で、自分たちの価値観の中で、自分たちの考える「政策」がまかり通っていくのです。
結果的に、東京の永田町や霞が関の机上で考えた、地方の実情とはかけ離れた「地方創生策」が行われることになります。
地方創生を「自分ごと」として捉えない役場職員
こんな状況ですから、いくら政治家や官僚が中央で考えた政策を押しつけても、地方は変わりません。
むしろ地方の役場職員も町の人も、そういう中央からの「政策」を見切っていて、「自分ごと」として地方創生を捉えられていない。自ら自分の町の長所や特徴を探ろうとしない。
横並びの発想しかない。勇気を持って一歩踏み出そうとしない。
たとえば「地域おこし協力隊」の採用状況がそうです。
一方では、北海道の東川町のように約80人も採用している町もあるというのに、ひとりも採用していないとか1~2人の採用でお茶を濁しているところもある。
そういう自治体の職員に聞くと、「協力隊員の3年後の定着率に課題がある。定着ができないならば採用しないほうがいい」と言います。ところが、それを理由に1~2人の採用では、定着率は0(%)か50か100かの博打になります。
















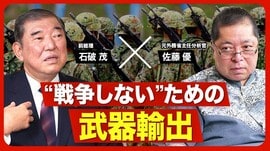














無料会員登録はこちら
ログインはこちら