心臓病や脳血管疾患など急性期の病気で入院したとき、同じように2週間以内に退院してほしいと言われた経験のある人もいるのではないだろうか。
これは、2006年から、厚生労働省が全国の病院の入院期間を短くするために、急性期病院に一定期間以上入院したら病院が損をする仕組みを導入しているからだ。
全国一律の入院費や診療費などの価格を決めている診療報酬の急性期の入院基本料は、2024年度の診療報酬では、入院日から14日間までは加算が付いて最高額がもらえるのに対し、入院15日目以降は加算額が減る設定になっている。
つまり、2週間以上入院する患者が多ければ多いほど、病院の経営状態は悪化する。
確かに、急性期病院の役割は急性疾患の治療なので、治療が終わった患者は次の救急患者のためにベッドをあける必要がある。もしもすべてのベッドが埋まってしまっていたら、新たに救急患者が出たときに助けられなくなってしまう。
とはいえ、治療が終わったかどうかに関係なく、Nさんが入院した病院のように、入院基本料が下がる15日目より前に退院させようとする病院が多いのが実情だ。
地域包括ケア病棟でも「退院してほしい」
Nさんは心不全も併発しており、骨折で入院して動けなくなったのをきっかけにいっきに体力が落ち、寝たきりに近い状態になった。横になっていても呼吸が苦しいため、本人も「不安だし苦しいから、家には帰りたくない」と話す。
そこで、急性期病院で治療を受けた後、2週間後に地域包括ケア病棟へ転院した。
地域包括ケア病棟は、急性期治療を終えた患者や一時的に入院が必要になった患者を対象に、リハビリや在宅療養の準備を整え、在宅復帰を目指すための入院施設だ。脳血管疾患や骨折などでリハビリが必要な人の場合は、急性期病院の後、回復期リハビリテーション病棟へ行く選択肢もある。
Nさんは息も絶え絶えで食欲も減退していたが、地域包括ケア病棟に移ってからは、ゼリーや流動食を少しずつ食べられるようになった。
急性期病院の慌ただしい雰囲気とは異なり、看護師が毎日の様子を教えてくれるなどケアが充実しており、長女はこの病院が気に入っていたが、地域包括ケア病棟でも、「1カ月くらいで退院していただきたい。自宅へ帰れないのなら、早く入所できそうな高齢者施設を探してください」と迫られる始末だった。


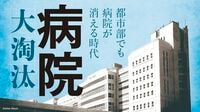




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら