医療法では病院を大きく、一般病床と精神病床などに分けている。
外見からは分かりにくいが、一般病床は、さらに、主に命に関わる病気などの治療をする高度急性期病院と急性期病院、その次の段階ともいえる亜急性期、リハビリを中心とした回復期、主に療養を目的とした病院に分けられる。
高度急性期、急性期、亜急性期の病院は、患者の人数に対する看護師の数によって、診療報酬で得られる保険点数が決まっている。
制度が複雑過ぎて医療関係者でも分かりにくいのだが、同じ病院の中に、急性期病床、回復期病床、療養病床など複数の機能の病床を持つ病院もある。
療養型の病院には、公的医療保険を使う医療療養型と介護保険を使う介護療養型があったが、この2つがほぼ同じような患者を受け入れていることが判明したことと、社会保険料を負担する現役世代の負担を減らす目的もあって、厚生労働省は2017年で介護療養型を廃止することを決定した。
移行期間を経て、要介護認定を受ければ比較的簡単に入院して長期滞在できた全国の介護療養病床は2024年3月末に廃止された。
療養型の病院の代わりになる病院の1つとして、2014年の診療報酬改定で「地域包括ケア病棟」が新設されたが、急性期病院での治療が終わった患者を自宅へ戻す在宅復帰を目標にした病棟であり、自宅へ帰れるような人しか受け入れないし、高齢者が長期間入院できる病棟ではない。
2018年くらいまでは、例えば、私の専門である脳神経外科分野でも、大学病院や大病院で手術を受けた患者は、すぐに自宅へ帰れない状態なら、手術後の患者のケアをしたり療養させたりする療養型の病院でリハビリや療養をしてから自宅や高齢者施設へ移ることが多かった。
しかし、医療費を削減したい財務省の締め付けの影響もあって、亜急性期や医療療養病床の診療報酬は削減され、これまで大学病院や大病院で命に関わるような病気の治療を受けた後などに、自宅へ帰れない人の受け皿となっていた病院が減っている。
自宅や特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどで暮らしている高齢者が、肺炎や心不全などで入院しなければならない状態になったときに、そういった病気の治療をするために入院できる中小病院も、経営が立ち行かなくなって減少中だ。
2週間以上の入院で病院が損をする
東京都内に住む85歳の女性・Nさんは、2024年2月、家の中で転んで尻もちをつき動けなくなった。
50代の長女が救急車を呼び、近くの急性期病院に搬送され腰椎の骨折と脱水症と診断され、心不全もあったのでそのまま入院した。救急搬送中には3カ所の病院に受け入れを断られていた。
入院が長期化しやすい高齢者を受け入れたくない救急病院は多いのだ。
受け入れ先が決まってほっとしたのも束の間、入院手続き時に長女は、病院のスタッフから「2週間後には退院してもらいます。すぐに転院先を探してください」と言われ愕然としたという。


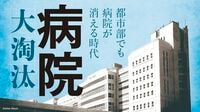




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら