地域包括ケア病棟では、2024年3月までは60日、同年4月からは入院期間が40日を超えると診療報酬の入院基本料の1日当たりの単価が減額される仕組みになった。また、病院の収入となる入院基本料は在宅へ戻れた患者の割合である在宅復帰率によって変動するため、病院としても自宅へ帰れないような患者は早く他の病院か施設へ移ってほしい。
これは、急性期病院で治療を受けた後にリハビリテーションをするための病院である回復期リハビリテーション病棟も同じことで、重度の脳血管疾患や脊髄損傷は最大180日、急性心筋梗塞や多発骨折などは最大90日と、疾患によって入院期間が決められている。
ちなみに、厚生労働省が診療報酬で急性期病院の入院基本料を15日目以降下げて在院日数を減らそうとしているのは、社会保険を圧迫する医療費総額を下げたいということに加えて、国際的にみて長過ぎる日本の入院期間を少しでも短くしたいとの目論見がある。
何しろ、日本の急性期病院における平均在院日数は、先進7カ国(G7)の中でも突出して長く、1995年には一般病棟でも30日を超えていた。厚生労働省の在院日数減少政策が功を奏して平均在院日数は半減し、2019年には16日になったが、それでも欧米諸国より長いのが現状だ。
そして、急性期病院や療養型の病院なども含む全病床の平均在院日数も、社会的入院が問題になった1970年代から90年代に比べると半減しているものの、約27日(2019年)でやはり、OECDの中では最も長い。
韓国も15日を超えているが、それ以外の国は10日以下だ。ちなみに、社会的入院とは、すでに治療が終わって病状が安定しているのに、居場所がないために生活上の理由で入院している状態を指す。
必要悪として存続する未届け老人ホーム
在宅介護が受けられる状態まで回復しなかったり家族による介護が受けられなかったりして、地域包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟から自宅へ帰れない高齢者は、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームなど、介護保険を使って入所できる施設を探すしかない。
特に東京23区内では、特別養護老人ホームは常にいっぱいですぐには入所が難しいし、心不全が安定しないなど医学管理が必要な人は受け入れてもらえないことが多い。
介護付き有料老人ホームは、年金収入が月20万円程度はあるか、貯金や土地をたくさん持っている資産家、あるいは息子や娘の手厚い援助が受けられる人しか入れない。
だから、未届け老人ホームが、必要悪として存続することにもなっているのだ。
用心棒をつけているようなところは別として、未届けでも、低価格で高齢者の居場所を提供しているのだから、多少劣悪な環境でも仕方ないと開き直っている施設運営者もいるのかもしれない。


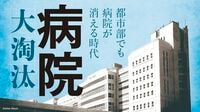




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら