扱いづらい、浮いている…「モンスター社員」を生み出しやすい企業の残念な"思考回路"とは
会社に対して不満を抱いたり、違和感を覚えたりしても、それを表に出す人はそう多くはありません。ただ、なかにはそれを言動やふるまいでわかりやすく表す人もいます。
・会社の方針に対して頻繁に疑問を呈する
・指示された業務のやり方に従わず独自のやり方を貫く
・暗黙のルールや慣習に従わない
・業界の常識に異議を唱える
・コミュニケーションの仕方が周囲と合わない
こうしたタイプの社員に対して、「扱いづらい」「浮いている」と感じることもあるかもしれません。実際、職場によっては"モンスター社員"と呼ばれ、問題視されるケースもあるでしょう。「まさに今、モンスター社員に手を焼いている」。そんな人もいらっしゃるはずです。
「モンスター社員」の裏に潜む真実
もちろん、こういった言動はほめられたものではありません。では、その社員がすべて悪いのかといえば、必ずしもそう断言できない部分もあると思います。その背景には、ミスマッチが存在するかもしれないからです。
もし、このモンスターとされている人が別の会社に転職し、スタイルが見事にマッチしたら、モンスターどころか「有能」と評価される可能性もあるでしょう。人の能力には大差がなく、能力の差が出るのは環境とのマッチング精度――これが私の持論です。
他責思考で自分たちに非はないと思っている企業の採用チームほど、「モンスター社員」という言葉を口にし、一方で自責思考が強い企業の採用チームは、ミスマッチの研究を怠らず、ミスマッチが起こらないやり方の再現性を徹底的に追求する傾向があります。
今、企業側に求められているのは、ミスマッチを防ぐことに注力し、抽象的な概念である会社のスタイルだけでなく、そこで働く個人視点のスタイルを発信していくことにほかなりません。さもなければいつまでもミスマッチは減らず、上がり続ける採用難易度を下げることはできないでしょう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

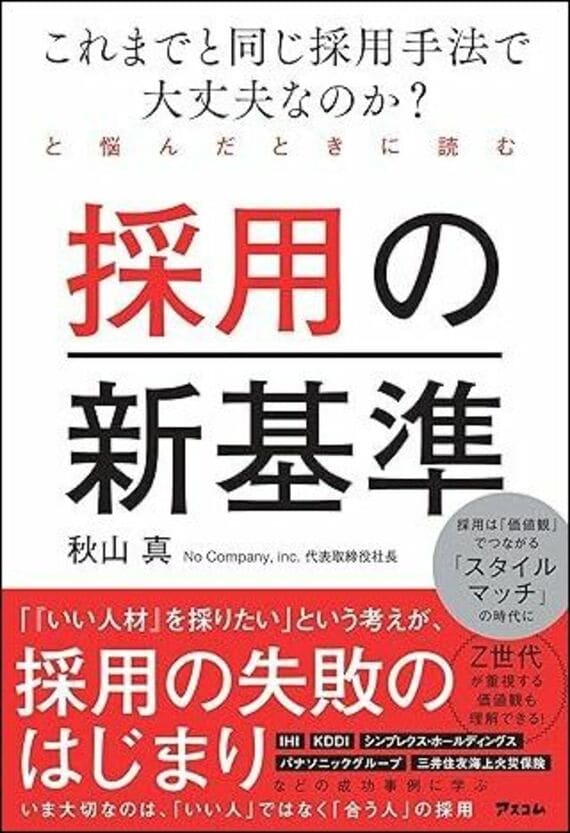
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら