この2つの特徴が合わさることにより、3つ目の特徴が生まれている。高齢になればなるほど、いくつもの非感染性疾患を同時に患う「多疾患併存」の状態になるケースが多くなるのである。
長く生きれば、どうしても加齢に伴う病気を患いやすくなる。英国王立癌研究基金(CRUK)の推計によると、1930年に生まれた人が生涯の間に癌を患う確率はおよそ33%だったのに対し、1960年生まれの人の場合、その確率は50%に達するという。
3秒に1人のペースで増える認知症
また、国際アルツハイマー病協会(ADI)によると、世界では3秒に1人のペースで誰かが認知症になっている。あなたがこの文章を読んでいる間にも、新しい認知症患者が生まれているのだ。
いま世界にはおよそ5700万人の認知症患者がおり(半分以上は低・中所得国の人たちだ)、その数は2050年には1億5300万人に達すると予測されている。
家族にとって、子どもたちの4人の祖父母がすべて健在なのはもちろん喜ばしいことだ。最近は、曽祖父母が健在のケースも増えている。しかし、ここには、不愉快な負担もついて回る。認知症を患っている人のおよそ4人に3人は、家族に世話されているという。
全米アルツハイマー病協会の推計によると、2010年に家族が高齢の親族のためにおこなった無給のケア労働は合計140億時間に上る。家族の介護と、仕事や余暇やその他の個人的活動のバランスを取ることは、多くの人にとってますます難しくなってきている。
こうした不愉快な統計上の現実は、老いることに暗い影を落とす。しかし、ファクトを丁寧に検討することが重要だ。それを通じて異なる視点が得られて、楽観論をいだく根拠も見いだせるかもしれない。
認知症は恐ろしい病気だ。この病気を患う人が増えていることが深刻な問題であることは言うまでもない。しかし、すべての人が認知能力の低下を経験するわけではない。ヨーロッパと北アメリカの推計によると、85~89歳の人のおよそ10人に1人が認知症を患っている。これは確かに気がかりなデータだが、裏を返せば10人に9人は認知症にならないのだ。




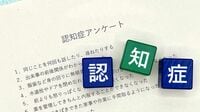




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら