春に入学したばかりの1年生が「やってみたい!」とMCに立候補することもあります。
周りはまだうまく話せないかもしれないとヒヤヒヤしますが、本人のやりたい気持ちを大切に、キッズコーチや上級生が横についてサポートしつつ、MCをこなしていく。ミーティングが終わったときの「やったぞ」という表情から、その経験が本人の自信につながっていったのが伝わってきます。
本人のやりたい気持ち大切に
また、1人では緊張してしまう子も、友達と一緒にMCをやってみんなの前に立つ経験を重ねていく。子どもたちは自分たちのコミュニティのなかで過ごしながら、人前で話す力、場を進行していく力を自然と身につけていくのです。
ときには、言葉遣いやルールの問題など、ちょっとした困りごとが話題になることもあります。小学生になると、友達同士の会話で「バカ」「死ね」といった言葉を口にしてしまうことも。
キッズミーティングでは、そうした言葉を注意するのではなく、「どうしたらいいかな?」と問いを投げ、一緒に考えることを重視しています。
正解を出すことが目的ではありません。さまざまな意見を出し合い、相手の立場に立って考えてみる。その対話の過程こそが貴重なのです。
「自分の意見を表明していい」という安心感が、子どもたちの発信力を育てていきます。すると面白いことに、ポジティブな雰囲気が施設全体に広がっていく。低学年で経験した子が高学年になると、今度は自分が下級生に伝える側に。子どもたち自身で、ポジティブなコミュニティを育んでいってくれるのです。
人間力は、人とのやりとりのなかで、ときには失敗しながら、少しずつ身についていくもの。だからこそ私たちは、子どもたち同士が安心して関わり合える場を大切にしているのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

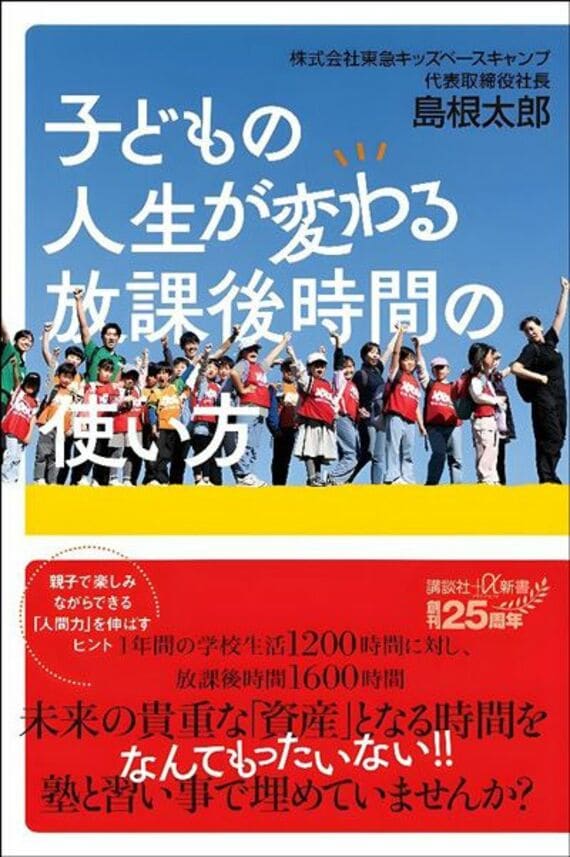































無料会員登録はこちら
ログインはこちら