
「非常に悲しく、大きな痛みを伴う決定だ」
2024年度(2025年3月期)に6708億円の巨額最終赤字(前期は4266億円の黒字)に転落した日産自動車。4月に就任したばかりのイヴァン・エスピノーサ社長は、四半世紀前の「日産リバイバルプラン」に匹敵する大規模リストラ策を取りまとめた。
2027年度までにグループ全体の15%に相当する2万人の従業員を削減(うち生産が1.3万人、販売管理が3600人、契約社員を中心とする研究開発が3400人)。さらに、国内外の車両工場を17から10へと減らす。
「やりたくてやるわけではない。ただ、いま手を打たない限り問題は悪化するだけ。残念なことにこれが日産の将来を救う唯一の方法だ」。5月13日の決算会見で、エスピノーサ社長はそう訴えた。
このほか、組織・部門の垣根を越えた300人のクロスファンクショナルチーム(CFT)を立ち上げて、車両の開発費用からサプライチェーンまでありとあらゆるコストを見直す。
「Re:Nissan」と名付けた今回の経営再建計画により、変動費2500億円と固定費2500億円、総額5000億円を削減。2026年度(2027年3月期)までに自動車事業の営業利益とフリーキャッシュフロー(CF)を黒字化させる。1999年、フランス・ルノーから派遣されたカルロス・ゴーン氏が国内5工場の閉鎖と2.1万人の人員削減を決めたリバイバルプランを彷彿とさせる荒療治だ。
遅すぎた抜本改革
「どうして前の経営体制でこうした改革ができなかったのか?」。複数の記者に問われたエスピノーサ社長は慎重に言葉を選びながら、「経営会議の多くのメンバーが交代し、危機感を共有した。会社としてよりスピードアップしなければならない」と答えるにとどめた。
日産は、昨年11月に9000人の従業員と2割の生産能力の削減を柱とする構造改革「ターンアラウンド」を示した。だが、生産能力削減は生産ラインの統合やシフトの調整、配置転換が中心。内田誠前社長や坂本秀行前副社長など当時の経営陣は工場閉鎖に消極的だったためで、市場関係者から「(改革の)規模も中身も明らかに踏み込み不足」と批判の声が出ていた。

日産の年間販売は2017年度の579万台をピークに、2024年度には334万台まで4割以上も低下。一方、グループ従業員数は2017年度末の13.8万人から2023年度末の13.3万人と大きく変わっていない。日産の工場稼働率は6割強と低迷しており、設備も人員も身の丈を超えたままとなっていた。
2万人の人員削減、日本を含む7工場の閉鎖は、日産に必要だった抜本改革がようやく打ち出されたといえる。

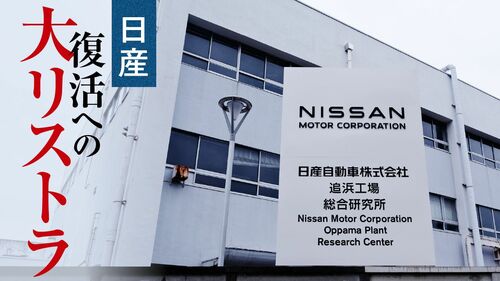

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら