資さんうどんが「東京でも通用した」のは、味の美味しさだけではない…全国進出に「失敗するうどんチェーン」「成功するチェーン」の決定的差
讃岐うどん店の2社(丸亀製麺・はなまるうどん)が全国チェーン店化に成功した理由は「セルフうどん業態の普及」「長時間・夜営業への対応」にあった。
もともと香川県内に多かったセルフ形態のうどん店は、来客が自らうどん・天ぷらを取ってくれるため、薄利多売なスタイルの飲食店としては効率が良かった。
しかし香川県では、製麺所併設型・自宅併設型の店舗が、家族経営でうどんを格安提供しており、夜にうどん需要が激減するため、昼過ぎには店を閉めてしまう。営業時間が短い上に夜営業がないと売り上げも獲れず、競争してまでうどん業界で定着を目指す勢力など、生まれようもなかった。
その中で「はなまるうどん」は、家族で行けるテーブル席中心のきれいな店で「かけうどん1杯100円(当時)」を提供、その分天ぷら・稲荷寿司などをプラスで頼んでもらい、単価向上で利益を稼ぐスタイルを編み出した。
一方で、兵庫県で創業した丸亀製麺は1日を通じてゆでたて・切りたてのうどんを提供し、高単価・高利益な新商品の投入で経営を安定させた。美味しさはもちろんのこと、丸亀・はなまるはセルフうどん業態で集客・利益を両立できたからこそ、そのビジネスモデルを掲げて全国チェーンへと飛躍できたのだ。

一方で「資さん」は、丼物などのメニューが充実した「うどんメインのファミレス」のような業態を編み出し、一人客からファミリー層まで「とりあえず行けば、何か美味しいモノが食べられる」豊富なメニューで顧客を獲得してきた。なお、「うちだ屋」も、「資さん」と共通点が多い「うどんファミレス」業態だ。
すかいらーくホールディングスも「資さん」が編み出した「うどんファミレス」の存在そのものが「稼げるビジネスモデル」であったからこそ、240億円という大金をはたいてグループに迎え入れたのだ。
こうして見ると、讃岐系・福岡系は味だけでなく、ビジネスモデルが高く買われている。両地域とも日常食としてうどんが定着していただけでなく、「サッと安く食べたい」(香川県)、「仲間うちで集まれる店が欲しい」(福岡県)という常連の要望に応え続けたからこそ、全国に通じるビジネスモデルに変化したといえる。
すでにチェーン店が存在 武蔵野うどんは全国に普及するか















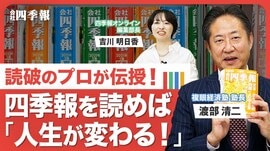
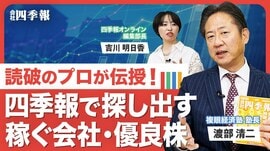






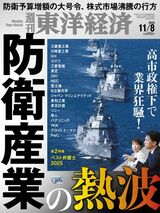









無料会員登録はこちら
ログインはこちら