池袋に増殖する「ガチ中華」の知られざる大変貌。おなじみの東北料理、四川料理だけでなく本格的な江西料理、ウイグル料理も堪能できる時代に
だが、ここ数年、SNSなどを介して中華料理に関する知識が増えたことに加え、日本人の食も多様化、「ガチ中華」という言葉が流行るくらい、日本人の中華料理に対する造詣も深くなっていった。その上、ガチ中華が増えた理由として、筆者は以下があると考えている。

① コロナ禍で日本人がなかなか中国に足を運べなくなったことにより、日本国内に本格的な中華料理を求めたこと。
② ここ数年、在留資格を取得しやすくなったことや中国人が経済的に豊かになり、(出身省別の統計はないものの)さまざまな省から来日する中国人が増加し、彼らの食の需要が増えたこと(在日中国人の人口は2014年末には約65万5000人だったが、2024年末には約87万3000人と、この10年で33%増加)。
③ 中国発の軽食チェーン店(たとえば福建省発の「沙県小吃」や山東省発の「楊銘宇黄焖鶏米飯」など)に加盟して、フランチャイズで店を開く在日中国人経営者が増えたこと。
④ 近年日本に移住した富裕層は日本で事業を行うための経営・管理ビザを取得することが多いが、そのビザ維持のため新規開店する人が多いこと。
このような理由から、いま、池袋西口や北口周辺を歩いてみると、東北料理以外、かなりマイナーなジャンルのガチ中華料理店の看板を目にするようになった。
細分化が進展
たとえば、2023年にオープンした新疆ウイグル自治区の民族料理店「西北料理 大新疆」をはじめ、湖南省の料理店「湘聚・湖南菜館」、甘粛省の料理「蘭州拉麺店 火焔山」、福建省の料理「福清菜館」、北京料理「東来順」などだ。さまざまな料理を同じ場所で食べられる軽食のフードコート「沸騰小吃城」、「友誼食府」、「食府書苑」も2019年以降にオープンした。

筆者が友人と一緒に行った江西料理店のように、経営者が江西省出身で、「東京で美味しい江西料理の店が少ないから」といって自ら開店するケースもあるし、福建省料理のように、東京近郊に福建省、とくに「僑郷」(華僑のふるさと)と呼ばれる福清市周辺からやってきた人が多く、福建省の郷土料理を食べたいという人の需要が見込まれるため、開店するケースも多い。
87万人以上という在日中国人のマーケットがあるため、ある省の料理というだけでなく、ある省の〇〇地方の料理でも経営が成り立つほど細分化が進んでいるのだ。







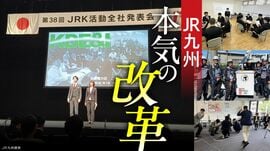





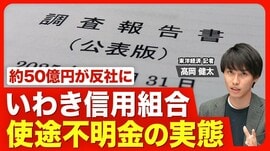
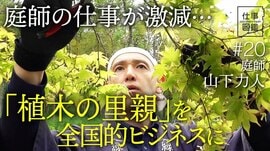

















無料会員登録はこちら
ログインはこちら