
今夏の参院選では「日本人ファースト」を掲げた参政党が躍進したほか、足元の自民党総裁選でも、奈良の鹿をめぐる外国人の行動が話題に上った(写真:freeangle/PIXTA)
いつの間にか、私たちが日本の社会や政治を語る言葉に、ほんの少し前までは海外の出来事を論じることに使われた「排外主義」という表現が入り込んだ。
朝日新聞のデータベースで調べると、この言葉が日本の出来事に使われ始めたのは1990年代の半ば以降である。それ以前は、海外の政治や社会を記述する際に使われた。それが今では外国人をめぐる国内問題に普通に使われるようになり、選挙のスローガンにまで登場するようになった。
記憶に新しいのは、国際協力機構(JICA)にまつわる誤情報の流布が巻き起こした事件である。アフリカ諸国との友好関係を強化するために地方自治体と特定の国々との関係に言及したことが思わぬ反応を引き起こした。そのときもこの言葉が多用された。
トピックボードAD
有料会員限定記事

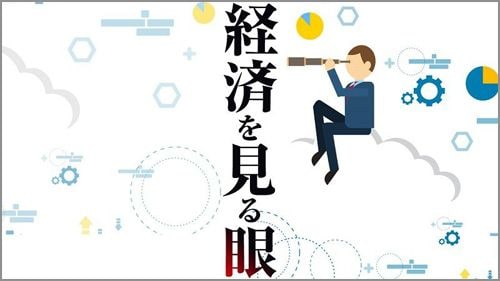































無料会員登録はこちら
ログインはこちら