「処理能力重視」から「思考力重視」へ、というこの流れは、数多くの入試問題で表れています。
理科は以前よりも問題のページ数が多くなり、図や実験から読み取って適切な公式を使う能力が求められるようになりました。公式を覚えているかどうかよりも、その公式がどういうもので、どのような場面で適切に使えばいいのかが求められるような問題が増えているのです。
社会でも、特に地理では「考えさせる問題」が増えて、単純な知識があればいいというわけではない問題が多くなっています。

誤解のないように注釈をしておくと、もちろん以前から思考力重視の問題はほかの大学に比べると多く出題されていましたし、今でも知識量が必要な問題や、処理能力がないと解けない問題も多いのですが、傾向として、その割合が「思考力重視」に傾いてきているということです。
なぜ、このような変化が起こっているのか? そしてこの変化は、東京大学にどんな変化をもたらすのでしょうか?
「東大=官僚養成大学」からの変化
みなさんは、「東京大学」というと、どんな受験生が合格しているイメージですか? なんとなく「頭のいい学生」というイメージは持っていると思いますが、より詳しく聞いてみると、「官僚になるような人」と回答する人が多い印象があります。
「東京大学=官僚養成大学」なんて呼ばれていた時代もありましたから、東大を卒業してから官僚になる場合が多く、だからこそ東大に合格する人は事務処理能力に優れた人が多い、という印象があると思います。
しかし、今は官僚という道を選ぶ東大生の数が少なくなってきており、代わりに「研究者養成」の方向に進んでいるのではないかと僕は考えています。
東大では、大学1年生から英語で論文を書く授業が始まり、学問の探究に主眼を置いた授業が多く展開されています。以前からもちろんそういう傾向はあったと思いますが、最近は官僚になる人よりも、研究職に身を置きたいと考える東大生の割合は増えているように感じます。
この変化が日本にどのような影響を与えるのかについては、まだわかりませんが、今後なんらかの変化を与える可能性は高いと思います。これからも注目していきたいですね。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


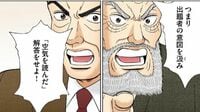





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら