「稀代のダメ男」キャラから学ぶ “メタ思考”の真髄 読書は「自分を客観視すること」に繋がる
だから私は、学生たちにいつも、
「本を読んだら、自分の経験に引きつけて考えてみてくださいね」
と言っています。
たとえば先ほどの太宰だったら、『人間失格』を読んでもらい、
「みなさんも道化のようにふるまったことはありますか?」
「うまく道化を演じたつもりだったけれど、ワザとだと周囲にバレたことはありますか? あるいは逆に、誰かの道化を見破ったことはありますか?」
といった問いを立てて、エピソードトークをしてもらう。そんな授業をしています。
私の仕事の大きな支えとなった言葉
私自身も、本を読むときは、必ず自分の経験に引きつけて、行動に生かしています。
たとえば『徒然草』を読んだとき、高校生だった私は、ある言葉に大きな刺激を受けました。それは、
「後(のち)の矢を頼みて、初めの矢になほざりの心あり」
という言葉です。これは、後の矢=2本目の矢を当てにしていると、初めの矢=1本目の矢にいい加減な心が生まれる、という意味です。
大きな刺激を受けた私は、すぐに自分の経験に引きつけて、こう決めました。
「そうだ、テニスのサーブを打つとき、ボールを2つ持つのはやめよう。1つだけ持って、1球勝負でファーストサーブを打つぞ!」と。
以来、いまに至るまで、この言葉はテニスに限らず、私の仕事を支える大きな支えとなっています。
このように本を自分の経験に引きつけて読むと、ただ文字を追うのと違って、メタ的に「さあ、この知識をどう実践しようか」と思考するようになります。
本の文脈と自分の人生の文脈。2つを重ね合わせるのが、「メタ思考読書」です。
このように本を読むことができれば、メタ思考が鍛えられること、間違いありません。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

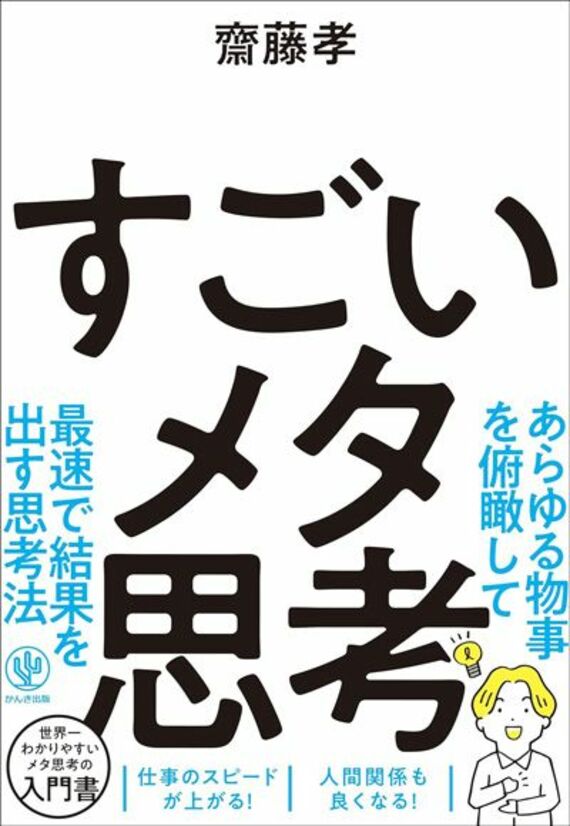

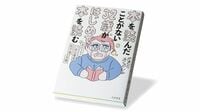




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら