「稀代のダメ男」キャラから学ぶ “メタ思考”の真髄 読書は「自分を客観視すること」に繋がる
そもそも主人公が道化を演じている、そのこと自体がメタ思考です。
主人公はなぜ道化になることにしたのか。
それは本当の自分が幼いころから人間を理解できず、世間とのズレを埋められなくて苦悩していたからです。
道化になれば、本当の自分をさらけ出さずに、人と関わっていくことができます。
小説のなかで太宰は、道化を演じることをこんなふうに表現しています。
「おもてでは、絶えず笑顔をつくりながらも、内心は必死の、それこそ千番に一番の兼ね合いとでも言うべき危機一髪の、油汗流してのサーヴィスでした」(『人間失格』新潮文庫)
やがて同級生に「ワザ。ワザ」と、笑いを取るためにわざと失敗したことを見破られて、また人間不信がぶり返してしまいます。
その後、太宰自身の転落の人生をなぞるようにストーリーは進んでいきます。
結局は不幸の連鎖を止められず、最後は病院に入って、「人間でなくなる」という結末。
何とも救いのない感じがしますが、読んでいるうちに自然とメタ思考が鍛えられます。
言うなれば、
「自分の不幸に対して、メタ的に立ち向かうことができる」
ようになるのです。
メタ思考によって“不幸耐性”が上がる、と言ってもいいでしょう。
無意識の思い込みをキャラが言語化する
古典的名著だけでなく、現代小説からも「メタ的な学び」を得ることはできます。
辻村深月(みづき)さんの小説『傲慢と善良』(朝日新聞出版)が、100万部を超えるベストセラーを記録しました。
この小説は学生たちにも大人気。私も早い時期に読み、若者がどこか息苦しさを覚える現代の婚活事情を描いたそのおもしろさに引き込まれました。
タイトルは、ジェーン・オースティンの名作『高慢と偏見』から着想したそうです。


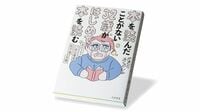




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら