「稀代のダメ男」キャラから学ぶ “メタ思考”の真髄 読書は「自分を客観視すること」に繋がる
こちらは18世紀末ごろのイギリスを舞台とした恋愛小説。結婚にまつわる女性の悩みが描かれ、その細やかな心理描写に卓越した人間観察眼が感じられます。
それはさておき、『傲慢と善良』で私が興味深く感じたのは、主人公の真実(まみ)が通う結婚相談所の女性が言った、次の2つの言葉です。
「(婚活に苦労している人は)皆さん、謙虚だし、自己評価が低い一方で、自己愛の方はとても強いんです」
「(中略)その人が無意識に自分はいくら、何点とつけた点数に見合う相手が来なければ、人は“ピンとこない”と言います。――私の価値はこんなに低くない、もっと高い相手でなければ、私の値段とは釣り合わない」
なるほど、「自分につける点数というのは、意外と高いのかも」と気づかされます。
でも、相手につける点数は低い。それで「釣り合わない」と感じた気持ちを、「ピンとこない」という言い方でごまかしている。
そんな心理が解き明かされると、読んでいる人は自分と重ね合わせずにはいられなくなります。
とくに、「自分は自己肯定感が低い」と思いこんでいる多くの人はハッとするのではないでしょうか。
「もしかしたら私、自己肯定感・自己評価が低いわりには、自己愛は強いのかも。婚活がうまくいかない理由は、その辺りにありそう」
というふうに、小説に刺激されて、自分を客観的に見るようになるのです。
作家の言葉、表現力は的確なので、読むうちに、無自覚だった自分の意識がはっきりする。そういうことはよくあります。
作家の頭脳レベルにどんどん鍛えられていく。上手な人とラリーをすると自然と自分も上達するように、メタ意識が養われるでしょう。
読書をもとに行動を変えていく
とはいえ、読書するうえで1つ、気をつけなくてはいけないことがあります。
それは「本の世界に惑溺してしまわない」ことです。
自分自身を忘れて、ひたすら本の世界にどっぷりつかるのは、「メタ思考読書」の本道からズレてますよ、ということです。
現実の世界から乖離すると、“書界の引きこもり”みたいになって感心しません。


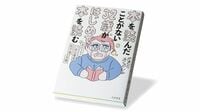




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら