「発達障害の子ども」に自信をつけさせるために…【小さな成功体験】を積み重ねるための"ちょっとした工夫"
「今、子どもがストレスを増やしすぎないために、必要だ」と判断したやり方を選んでもいい状況だってあります。子どもと向き合っている自分や家族を、たくさん褒めましょう。
「マナー」と「特性」の折り合いは、どうつける?
社会で生きていく上で例えば、マナーを守ることは大切なルールの1つです。保護者や子どもの預け先では、どのような子どもに対しても「お店の中では騒がないでおこうね」といった基本的なマナーの説明をしていると思います。また、1度きりではなく、繰り返し伝えることも既にやっていることでしょう。
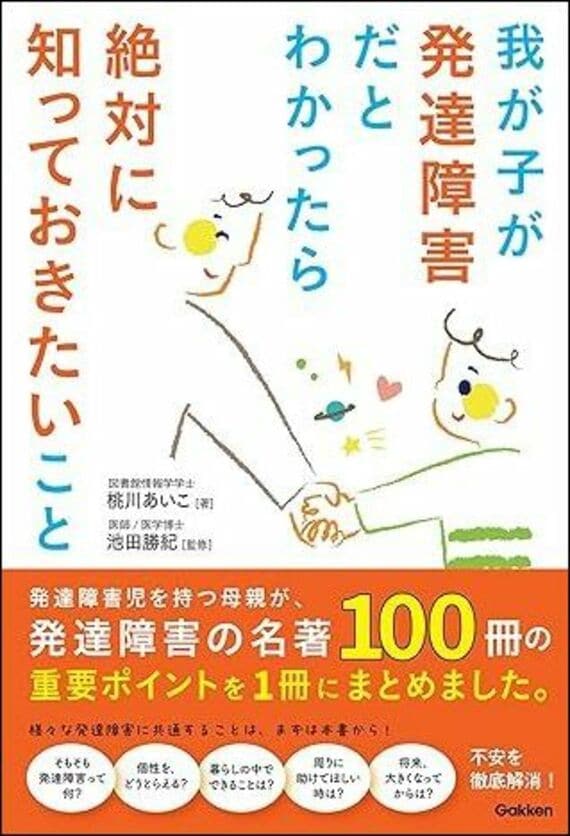
ですが子どもに感覚の過敏さという特性があると、大多数の人がやり過ごしていて何とも思っていないような刺激を強く受け取ります。
そのような環境や、子どもにとって不慣れな状況は、頭ではマナーを理解していても落ち着くことができなかったり、マナーに反した行動となってあらわれたりすることがあります。
特性に合わない環境(刺激)の例としては、次のものが挙げられます。
・ スーパーマーケット:人が多かったりさまざまな商品が並べられていたり、普段の暮らしよりも視覚的な刺激が強く、落ち着きをなくすことがあります。
・ レストラン:普段とは違う雰囲気や周囲の人の視線で緊張したり、慣れない場所の匂いに耐えられなかったりといった過敏さがあると、行動が不安定になることがあります。
基本的なしつけ(マナーの説明など)をすることや、目立つ特性をカバーできるようにアイテムを使うといった努力があったとしても、社会環境のほうに「その子に合わないもの」が含まれていたら、高い「マナー守れる度」を目指すことには無理があります。
先にマナーの型に子どもを押し付けるのではなく、まずは子ども自身のストレスを減らす工夫やその場所で楽しく過ごせる工夫をして、結果として穏やかに行動ができた(=マナーにも沿っていた)、という道筋が望ましいと考えられます。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら