「Not Like Us」ラップ歌詞が国境を越え刺さる訳 日本に20年住んで感じた恐怖や排除の反応
私が子どもの頃、学校は私とクラスメートに、私たちの偉大さは教科書の脚注に記されるものではなく、人類史の中心的な章に書かれているものであることをわからせてくれた。
「黒人は特別なのだ」という考え方は、私に力を与えてくれたが、大人になるにつれ、ほとんどすべての文化がこの物語を自らに言い聞かせていることに気づいた。多くの社会が、自分たちの例外性を根強く信じており、しばしばその物語を補強する方法として歴史を利用している。
日本に20年間住んだことで、私はこうした考えを検証するための別の眼鏡を手に入れた。日本もまた、他のどの国とも違うという独自性の物語を持っている。そして、この誇りは強さの源にもなりえるが、同時に、伝統的な型にはまらない人々が完全に受け入れられていると感じることを難しくすることもある。
過去を消そうとする者、取り戻そうとする者
私は日本の友人や家族から、これは意図的なものではないと言われ、額面通りに受け入れている。しかし最近、これは人間の本性なのだろうかと思うようになった。
私にとって、ラマーの「Not Like Us」のパフォーマンスは、単に馬鹿げたラップの確執についてのものにとどまらなかった。歴史、アイデンティティ、そして権力は、常に争いの中にあるということを思い出させてくれる。過去を消そうとする者がいる一方で、過去を取り戻そうとする者もいる。
そして、このメッセージはアメリカ国内をはるかに超えて、世界に響いている。「Not Like Us」というフレーズは、歴史を通じて、さまざまな社会で、さまざまな形で響いてきた。
アメリカでは抑圧と抵抗の両方に拍車をかけてきた。日本では、より微妙に、しかし永続的な結果をもたらす。問題は、単に「彼ら」が誰なのかということではなく、「私たちと同じ」「私たちとは違う」が実際に何を意味するのかを決めるのは誰なのかということだ。
政治であれ、歴史であれ、文化であれ、アイデンティティがゲームであることに変わりはないからだ。そして、誰が属し、誰が属さないのかというルールは、今もなお書き換えられ続けている。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら














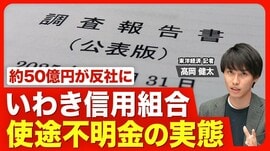

















無料会員登録はこちら
ログインはこちら