「不動産価値が下がらない街」には大きな特徴がある 「人の新陳代謝」が悪い街で起きることとは?
私はこの動きを「人の新陳代謝」と名づけています。人の出入りが多い、つまりエリアの人が常に一定数入れ替わることが空き家の発生を防ぎ、不動産価値を維持、向上させるのです。
都内ですら、すでにエリア間格差が生まれている
こうした視点で各エリアの人の動きと空き家の状況を紐づけしてみるとおもしろいことがわかります。各自治体の人の出入り、つまり毎年の転入者と転出者の合計を「新陳代謝数」とし、期初における総人口の何%が入れ替わったかを「新陳代謝率」(以下、代謝率)としました。そしてこの代謝率と空き家率の関係を分析したのが【図表12】です。

東京都を含む首都圏1都3県でこの代謝率と地価上昇の関係には明確な相関があり、代謝率10%を超えている、つまり年間で人口の1割が入れ替わるエリアで地価は上昇することがわかりました。この理屈で言えば、代謝率の低いところでは空き家が増えているはずです。
東京都の平均代謝率は12.7%ですが、【図表12】にあるように八王子市は8.0%、あきる野市や青梅市になると6.9%と人の出入り(代謝)が少ないことがうかがえます。
こうしたエリアでは当然空き家率も高い数値が計上されます。東京都の空き家率は10.9%ですが、【図表12】で掲げた自治体の多くが東京都平均を上回る空き家率になっています。またこれを個人住宅空き家率で比較しても、東京都平均2.6%を上回る自治体が目立ちます。
都区内でも足立区や葛飾区は代謝率ではかろうじて10%を超えて人口が増加しているものの、23区内順位は低い状況です。
人の出入りが少なくなる、代謝率が落ちると高齢化にともなって人口が減少し、新たに転入する人が減ることで、エリア内の住宅が空き家化していくのです。東京都内ですらすでにエリア間に格差が生じ始めています。空き家はすでに日本の首都でも深刻な問題となることを、これらのデータは雄弁に物語っているのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

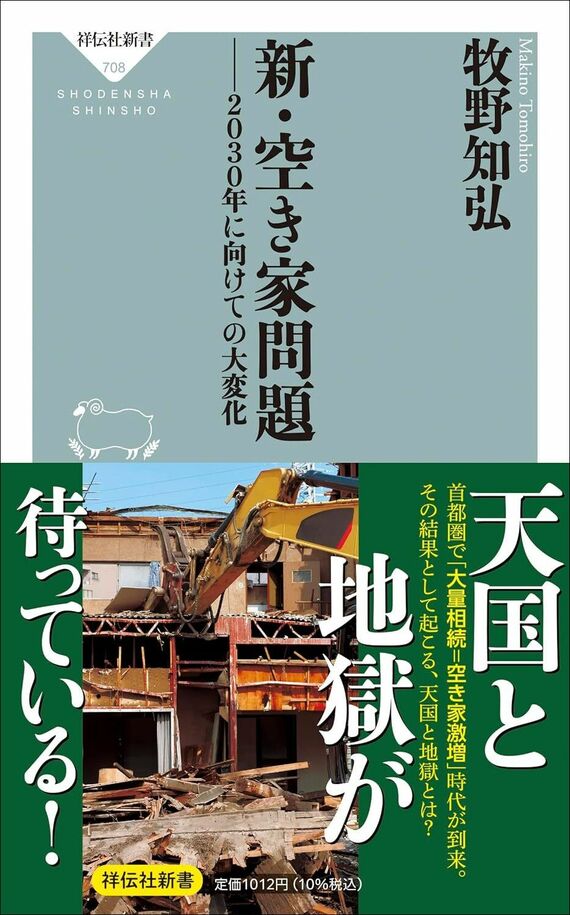






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら