
SNSで変わった番組のつくり方
僕がニッポン放送に入った2007年の頃には、「ラジオ番組は、あくまでラジオ局のプロが作って、リスナーに届けるもの」という考え方が浸透していました。
番組を聴いてくださるリスナーは大切な存在だけれど、リスナーの意見を聴き過ぎるといい番組は生まれない。そんな価値観が長らく固定されていました。
そもそも、SNSが普及する前の「リスナーの声」の見え方というのは、放送局にかかってくる問い合わせの電話、番組に直接届くハガキやメール、ファックスという、ダイレクトにメッセージを受ける手段しかありませんでした。
わざわざ番組にアクションを起こしてくださる方は、番組へのご意見、特に批判的な意見が多く、だんだんと真正面から受け止めにくくなってしまっていたのが実情でした。



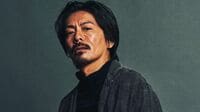





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら