佐藤:しかし論理や観念とは異なる手段で、異文化を理解することもできる。イギリス出身の名演出家ピーター・ブルックは、『鳥の会議』という芝居でバリ島の仮面を使いました。とはいえ欧米の役者が、バリ島の仮面劇の所作をただ模倣しても説得力がない。
そこでブルックの役者たちは、仮面を観察したり、その性質を探ったりすることで、自分と仮面の関係を見つけようとした。その結果、バリ島に伝わる所作とは異なる形で、仮面を使いこなすにいたったのです。役者の肉体を媒介にして、観念と実感を融合できるのが演劇の強みですが、九鬼はこのことを知らなかったのでしょう。
「偶然の必然化」は覇権志向への道
佐藤:以上の点を踏まえて、日本主義と世界主義に関する議論を検討します。九鬼は両者の関係について、無窮(=永久)の道徳的実践と規定しました。自己の個別性・特殊性を尊重しつつ、異質なものに触れることで自己を解釈し直し、その結果、「個別的なものの総合」たる普遍のあり方も再解釈するというプロセスです。
では、なぜそんなことをしなければならないか。九鬼の言葉を使えば「偶然の必然化」を実現するためです。どんな国の文化も個別性を持っていますが、それが単なる偶然の産物でしかなかったら、そんな文化はあってもなくてもよいことになる。言い換えれば、われわれ自身の存在も、あってもなくてもよいものになってしまいます。アイデンティティを安定させるには、個別性を「偶然の産物」にすぎないものから、必然的なものへと高めねばならない。
しかし「必然に高める」ためには、おのれの個別性の中に普遍性が宿っていると構える必要がある。普遍性に到達するのは不可能とされているものの、偶然の必然化をめざす行為自体が、普遍性の追求へと不可避的に行き着くのです。けれどもこうなると、十分に必然化された文化は、普遍性を実質的に獲得しているはずだという話になる。
文化は本来、ひとしく偶然的であり、ひとしく個別的です。すべての文化がそれぞれの個別性を持つことで、世界の文化が成り立っている。しかし偶然の必然化をめざすのは、「必然化の進んだ文化は、普遍性を実質的に獲得している点で、偶然性の段階にとどまっている文化に優越する」ことを認めるにひとしい。
ジョージ・オーウェルの『動物農場』に登場した有名なフレーズではありませんが、「すべての文化は平等である。ただしある種の文化は、他の文化よりも、もっと平等である」。特定の文化による覇権が正当化されてしまうのです。となれば、他の文化に属する人々は、覇権的な文化への適応を必然的に求められる。九鬼の議論が、グローバリズムを否定するものになりえたとは到底言えません。




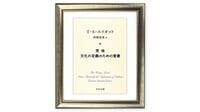


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら