ゲーセン「大量閉店」の背後にある本質的な変容 「千円でだらだら」若者の消費欲を満たせてない
加藤裕康は『ゲームセンター文化論』という本の中で、かつてのゲーセンが若者たちにとって、どのような場所だったのかを書いている。
この中では、ゲーセンに集った人々が、お互いのことをハンドルネームで呼び合い、また、ゲーセンの中にあった「ゲーセンノート」というノートの中で若者特有のコミュニケーションが生まれてきた様子が書かれている。
若者が集い、たむろする場所としてゲーセンがあったことがわかる。
さまざまな若者を受け入れ続けてきたゲーセン
もちろん、ゲームセンターと一口にいってもその歴史は古く、その中でさまざまに変化を遂げつつ、そのたびに客層を変えてきた。
1980年代には、「スペースインベーダー」(1978年)のヒットを受けて、ゲームセンターが増殖。一方で、その店内の薄暗さも相まって「不良の溜まり場」としてのイメージを強く持たれることになる。今でもSNSをたたけば、当時の暗かったゲーセンで不良にカツアゲされた思い出を書く人もいる。
治安という面では望ましいことではないが、あるタイプの若者たちの居場所にはなってきていたのだろうと思わされる(もちろん、不良ばかりがいたわけでもないが)。
そうした状況を受けて、1990年代以降は「アミューズメント施設」へと舵を切り、縦型のアーケードゲームやプリクラも増えてきた(先立つ1985年に風営法が改正されたことが大きい)。
すると、今度はプリクラを撮るために女子高生が集まる。また、1990年代から、いわゆる「音ゲー」も全盛期を迎え始め、凄腕の「音ゲーマー」がプレイする周りには、見物客が多く集まるようになった。ある種のコミュニケーションがそこから生まれ、「そこに行くだけでなんだか楽しい」場所として、ゲームセンターはあったと思う。
私も友人がこぞってプレイしていたから、なんとなくわかるが、100円でけっこうじっくり遊べるのが「音ゲー」だった。「せんだら」の文脈からいえば、1000円も持っていけば、かなり満足いくまで遊べるのが音ゲーだったのではないか(ちなみに私の友人は金持ちだったらしく、1000円以上使っていた。うらやましかった)。
いずれにしても、その客層は異なれど、若者が集まる場所としてゲームセンターは機能していたと思う。そして、それは、あまりたくさんお金を使うことなくいられる場所だったから、ということもあるだろう。
















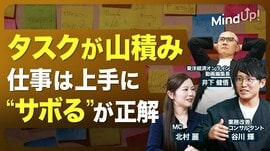















無料会員登録はこちら
ログインはこちら