その寺は山深く分け入ったところにあった。三月も終わろうという時期で、京の花はみなもう盛りを過ぎている。けれども山の桜はまだ満開で、分け入っていくにつれて広がる霞(かすみ)がかった光景を、光君は興味深く眺めた。こうした遠出の外出も今までしたことのない窮屈な身分なので、珍しく思えるのだった。寺の様子もじつに趣深いものだった。峰が高く、岩に囲まれた奥深いところに、その聖はこもっていた。光君は素性を明かすこともなく、またたいそう地味な身なりをしてはいるが、そのたたずまいから高貴な人だとはっきりわかったらしく、聖は驚きあわてている。
「これは畏れ多いことです。先日お召しのあったお方でしょうか。今は現世の俗事と縁を切っておりますので、加持祈禱(かじきとう)の修行もすっかり忘れておりますのに、なぜこのようにわざわざお越しくださいましたのか」と聖は笑みをたたえて光君の姿を眺める。いかにも尊い感じのする高徳の僧である。しかるべき護符などを作っては光君にのませ、加持祈禱をはじめる。そうしているうち日も高く上った。
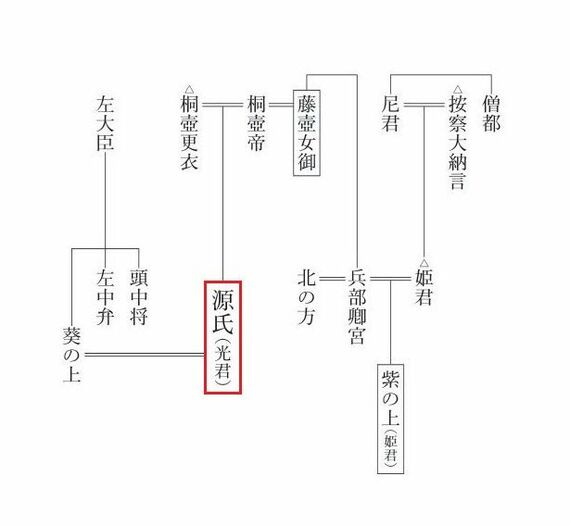
幾重にも折れ曲がった山道に
岩屋から外に出てあたりを見やると、高いところなので、あちこちにいくつもある僧坊が見下ろせる。幾重にも折れ曲がった山道に、ほかの僧坊と同じく小柴垣(こしばがき)ではあるが、きちんと周囲にめぐらせて、家屋も渡殿(わたどの)もこぎれいに立て並べ、木立もまた風情のある庵室(あんしつ)が一軒あるのを見つけ、
「だれが住んでいるのだろう」と光君は訊(き)く。お供のひとりが、
「あの何々の僧都(そうず)が、この二年のあいだこもっているところだそうでございます」と答える。
「立派な人の住んでいるところなのだね。みっともないほどみすぼらしい恰好(かっこう)で来てしまったな。私のことが耳に入ったら困ってしまう」
こぎれいな女童(めのわらわ)たちが大勢出てきて、仏に水を供えたり、花を折ったりしているのもはっきりと見える。






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら