SNS多用する人に伝えたい、相手を傷つけない技術 文字によるコミュニケーションが難しい理由
少し想像してみてほしいのだが、あなたがいいところを見せたいと思っている観衆の前に立っているとき、プライベートで1対1で議論しているときと比較して、どれくらい猛烈に自分の立場を守ろうとするだろうか。
途中で考えを変えたり議論に「負ける」ことは屈辱的だと捉えられるため、ソーシャルメディア上の議論が多くの場合、悪い方向に捻れてしまうのも、まったく驚くことではないことが分かるだろう。
公開での会話とプライベートでの会話は違う
逆に、ソーシャルメディア上で会話をもつことの利点は、主に2つある。そしてそのどちらも、公開のソーシャルメディアで行うことを必要としない。
2つの利点は要するに、デジタル・テキストを通じたやりとりは、色々な弱点はあるものの、時間や空間の制約がない、ということでまとめられる。
インターネット接続さえあれば、リアルタイム通話が低コストかつ地球上のほとんどすべての場所にいる人とあっという間にできてしまう。
それに、答える前に少し考える時間を取ったり、落ち着く時間がほしいと思うような質問をパートナーが投げてきたら、必要なだけ時間をとることができる。
この性質のおかげで、対面だとしばしば会話を脱線させかねない、感情的なリアクションを抑えることができる。
こういう点は確かに、紛うことなき利点だと言える。
しかし再度強調しておくと、公開での会話とプライベートでの会話は違うということを忘れてはならないし、揉めそうな話題に触れ始める前には、プライベートに切り替えるようにすることだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

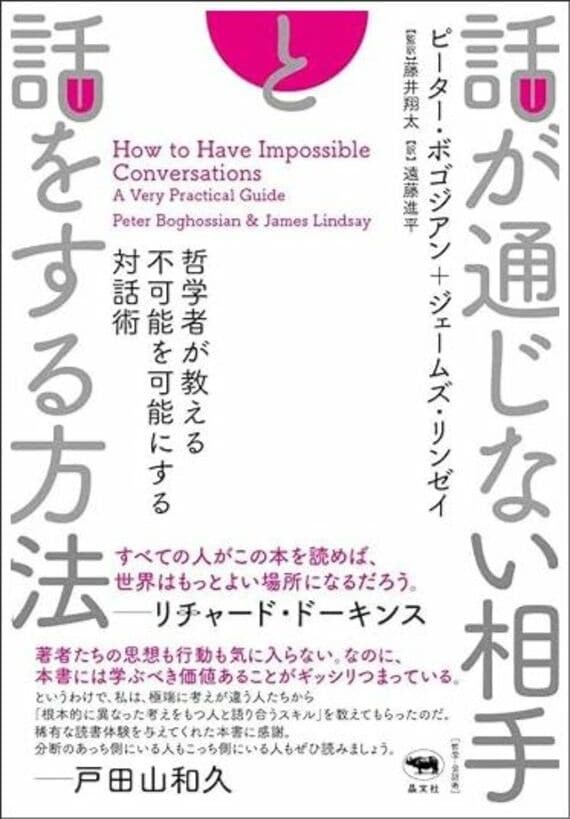






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら