「勝ち組でいたい」に縛られる人が行き着く場所 その価値観は刷り込まれたものかもしれない…
「あれは進んでて、これは遅れてる」なんて思い込み?
フランスの文化人類学者、民族学者。構造主義の祖とされる。著作『悲しき熱帯』など。
・未開社会のなかに飛び込んだレヴィ=ストロース
構造主義は、1960年代に登場して、フランスを中心に発展した思想です。構造主義を誰が唱えたのかという線引きをすることは難しいのですが、言語学者のソシュールによる「構造言語学」に影響を受けた文化人類学者のレヴィ=ストロースによって、一気に広まった思想であることは間違いありません。
レヴィ=ストロースは、先住民のなかに飛び込んで親族関係や神話などの研究をしていました。そこで親族関係の構造分析を通して、未開と呼ばれる社会にも、文化と自然を調和させる仕組みや独特の思考法があることを発見し、それを「野生の思考」と名づけました。
・構造主義のヒントになったのは「言葉と音の関係性」?
そもそも、構造主義の「構造」とはなんなのでしょうか。レヴィ=ストロースが「構造」のヒントを得たのは、ロシア人言語学者ロマーン・ヤコブソンの音韻論です(ヤコブソンは、ソシュールが提唱した構造言語学の原理を発展させました)。ヤコブソンによると、言語はそれ自体が本来的に意味をもっているのではなく、発音と言葉の関係によって意味が生まれているそうです。
たとえば「r」と「l」という音はまったく違った発音をされるので、英語ではrice は「米」ですが、lice は「シラミ」を意味します。しかし、日本語ではrとlの区別がないので、「ライスをください」といえば、それは「米」以外なにものも意味しません。このように、言語が異なれば音素とそれが指す内容の関係も異なるというわけです。このような関係性を「構造」といいます。構造は表には見えてきませんし、無意識的に潜在しているという特徴をもちます。
・構造は、あらゆる現象にある!
レヴィ=ストロースは自然学者トムソンの説も応用します。トムソンによると、魚の形を座標に乗せて、その座標自体を変形するといろいろな種類の魚の形になるといいます。魚のイラストを上下左右に縮小拡大するイメージで、たとえばフグの座標を変形するとマンボウになります。
このように、あらゆる出来事は変化していきますが、その「構造」(この例でいうと、魚の形の関連性)は維持されます。レヴィ=ストロースは、この「構造」の考え方を未開社会に適応したのです。
・西欧社会が未開社会より進んでいるわけではない
レヴィ=ストロースにより、未開の社会における親族・親戚・婚姻などの関係は、西洋におけるそれと「構造」という観点では変わらないことがわかりました。
彼は「野生の思考」とはすなわち具体の科学であって、今までの「近代的思考だけが理性的だ」という先入観を批判しました。自民族中心主義にかたよった西洋の世界観・文明観に根底的な反省を促したのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

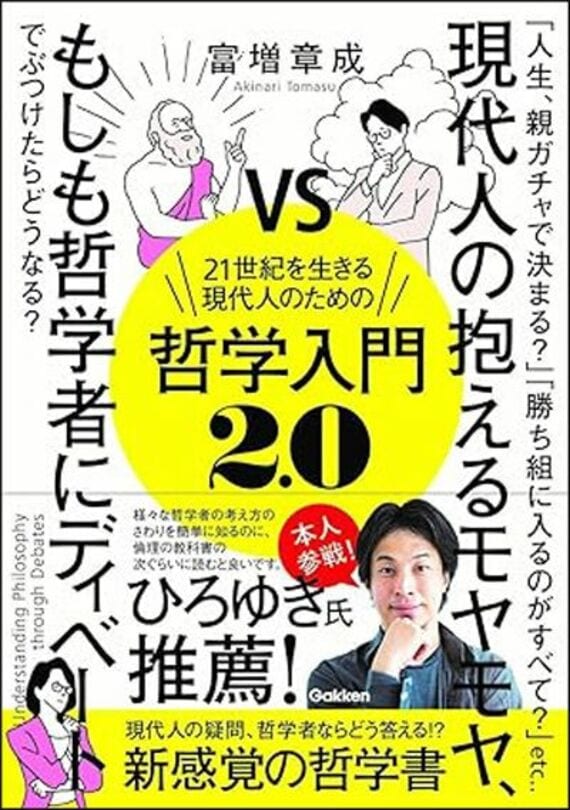



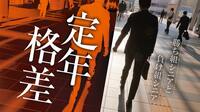


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら