デザイン思考の壁を突破する哲学シンキングとは 哲学はビジネスの場面で大いに活用できる
メソッドや企業での導入例は書籍に譲るとして、ここでは用途を紹介すると、先の図のようにデザイン思考のプロセスに取り入れることで、上記の問題点を解決する手立てとなります。
「なんのために自分たちはこのプロジェクトを進めるのか」「このプロジェクトを通じて何を実現したいのか/したくないのか」「コンセプトやキーワードについてチームで同じ意味を共有できているか」「チームメンバーが本音を語り合い、結束力の高いチームビルディングを実現できているか」など哲学的に問うことで、思考のフレームを拡張したり、立ち返るべき理念や価値判断の基準を確立したりすることができます。
その基準は、アイデアや問題定義の選択基準、またはプロジェクト終盤での検証基準にもなります。
哲学的なレベルまで掘り下げて問い、目指すべき理念や本音を共有することでプロジェクトメンバー同士のチームビルディングが達成され、真にクリエイティブな土壌が耕されます。
「なぜ5回」では解決できない場面にも有用
デザイン思考のステップ1「観察・共感」に先立って哲学シンキングを取り入れると、チームで何をなすべきかが明確になると先述しましたが、組織のビジョン構築・共有や、商品開発・サービス設計・広告制作においても、なぜそれをやるのか、それをやることが自分たちにとってどういう意味があるのかを問う必要があります。そうした場面で、理由や意味を問い詰めて考える哲学シンキングは有用です。
ビジョンやコンセプトについて同じ言葉を使っていても、各々が理解していることが一致しているとは限りません。プロジェクトが進んでいくなかで、それぞれが実は違うことを考えていたことがわかったという経験がある方もいるのではないでしょうか。
こうした場面においては、「なぜを5回問いなさい」といったビジネスにおける教訓もあります。
しかし、「なぜ」を問うことはそれほど容易ではありません。「なぜ」という問いかけは、「○○だから△△である」と根拠や理由を問うこともあれば、「Aが起きてBが起きた」と原因を問うこともあります。また、「○○のために△△する」と目的を問うこともあります。「なぜ」という問いへの回答のパターンはたくさんあるので、本来は「なぜ」を分解・細分化して問わなければいけません。




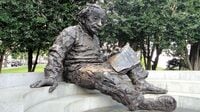


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら