デザイン思考の壁を突破する哲学シンキングとは 哲学はビジネスの場面で大いに活用できる
仮に、ステップ1の「観察・共感」からさまざまなインサイトや着眼点を得られた場合も、その解釈の仕方が複数あったとしたら、ステップ2でどのように問題を定義したらいいのかという問題もあります。
ステップ3の「アイデア創造」では、ある問題定義に対していろいろな問題解決のアイデア候補を列挙したとしても、それらのうち何をどのように選べばいいのでしょうか。
企業側の思いやビジョンが求められている
こうした問題点に対する対処策は、ユーザーが何を求めているか深く知るための本質的な問いを立てること、そして企業側が「自分たちはどんなことに問題を見出し、何を実現したいのか」を明確化することです。
ユーザーへの「観察・共感」も重要ですが、どのように問題定義し、どんなアイデアを採用するかは企業側の価値基準次第です。ユーザーが何を欲しているかだけではなく、企業側の思いやビジョンが求められつつあります。
もしそうした基軸がなかったとしたら、たまたま選択された問題定義やアイデアが、プロジェクト全体や会社全体の方針と齟齬を起こすこともありえます。近視眼的にはある特定の問題を解決するように見えても、中長期的に利益よりも損失のほうが大きくなることもあるかもしれません。
こうした諸問題に対して哲学シンキングは、その解決策=ソリューションとなりうる思考法です。




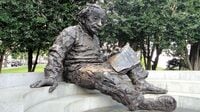


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら