人生100年時代を迎え、変化の激しい社会を生き抜いていくには、今までの知識伝達型の学び方では、必要な力は身につきません。しかし日本の標準的な1クラスの人数は40人で、諸外国と比べ圧倒的に多く、主体的な学びにおいて理想的な環境とはいえません。学び方を変えたくても、学習環境を一気に変えるわけにはいきません。
そこで登場したのがGIGAスクール構想です。学習者主体の学びを実現するために、必要な環境を整備しようというのが狙いとなっています。
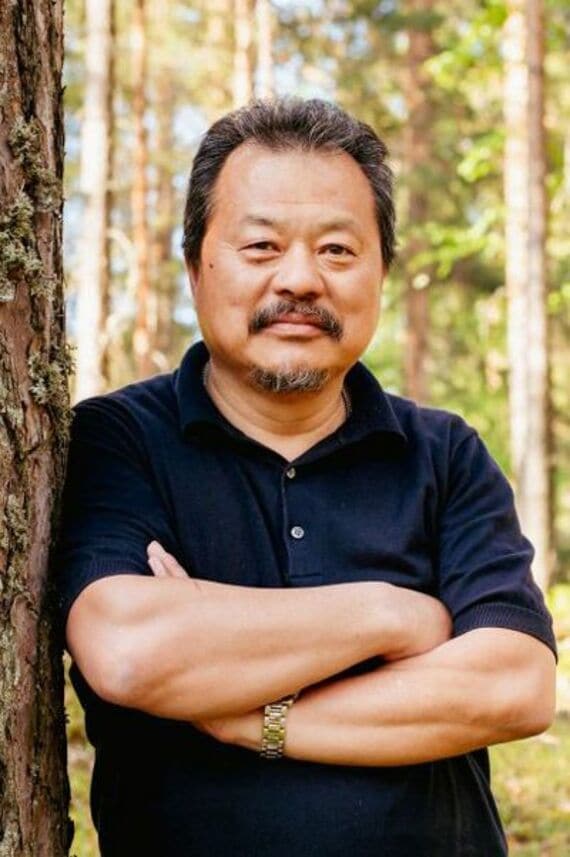
現状、GIGAスクール構想により、生徒一人ひとりに1台のデバイスを与えるという目的は果たしましたが、使用頻度は積極的に取り組んでいる自治体と、そうでない自治体とで差が出ています。実際、文部科学省が毎年度実施する「全国学力・学習状況調査」でも、自治体格差が顕著に表れています。
「ICT機器を授業で活用している学校の割合」では、ICT機器を週3日以上活用している学校が約8割です。ところが、「自分で調べる場面でICT機器を使用している学校の割合」はそれが6割に下がり、「自分の考えをまとめ発表・表現する場面でICT機器を使用している学校の割合」となると4割まで下がります(いずれも「ほぼ毎日」「週3回以上」の合計。政令市を除いた小学校の都道府県別データ)。
さらに「児童同士がやり取りする場面でICT機器を使用している学校の割合」は、月に1回未満を含めても3割弱に下がり、月1回未満の学校が激増しています。
つまり、ここがICT機器活用の大きな分かれ目です。「自分の考えをまとめ発表、表現する場面」の活用は従来の授業の中でのICT機器活用であり、ここでの学びは教員と子どもを結ぶ縦のラインの学びと言えます。一方で子ども同士のやり取りのある学びは、横のラインの学びと言えます。ここがICT機器活用により学びが変わる大切なポイントとなるわけです。
言い換えれば、子ども同士のやり取りを意識した授業を展開すれば、学びが変わる可能性が高くなるとも言えるでしょう。
子どもたちに学びを預けることで、自分たち自身で学びをどんどん深めていきます。任せることに不安を感じていた教員も、その姿を見て、「子どもたちは意外とやる」と、意識が変わります。意識の転換を図るうえでも、子ども同士で学ばせることに大きな意味があると思います。
学校こそAIやChatGPTとも上手に付き合える
子ども同士で学ばせることに貢献できるのがICTです。たとえばクラウドを使ってデータを共同編集したり、友だちの作品にコメントを加えたりするなど、工夫次第でいろいろなことができます。
クラウドを使いこなすと、ICTスキルが一段上のフェーズに入ります。学校は、今自分たちがどういう立ち位置にいるのか確認して、次へ向けてステップアップしていくことが大切だと思います。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら