テレビ放送との違いは、以下にある。
②膨大な番組数から好きなコンテンツを選べるという、限られたチャンネル数の制約からの解放、
③倍速視聴による「コスパ消費(コストパフォーマンス消費。単位時間あたりに多くのコンテンツを視聴したり、すきま時間に手軽に視聴するという意味)」の実現
「特に若年層では、コンテンツ視聴の目的が他人との情報共有に主軸が置かれているため、限られた時間内でいかに多くのコンテンツを消費するかが重要」という考察もある。
動画配信とテレビ放送の広告モデルの市場は、2021年の2兆1314億円から2028年には2兆3560億円へと緩やかに拡大していく。ただしその内訳は、この間に「配信」の比率が14%から32%へと大きく拡大する。ここでも、通信が放送を侵食していく構図が見て取れる。
メディアビジネスの主戦場は放送局からポータルへ
利便性が高い動画配信サービスだが、新しいプラットフォームをゼロから立ち上げ、そこに多くのユーザーを集めることは難しい。民放各社とも自社のプラットフォームを持ちつつも、共同運営のTVerやParaviといった配信ポータルを通じて多くのコンテンツを提供してそこにユーザーを集め、視聴率を取り、データを取り、効果的な広告を打つことで収益につなげている。
テレビ放送のマスリーチの大きさと広告効果にはまだまだかなわない部分も多いが、長期的にはメディアコンテンツビジネスの主戦場はテレビ放送から配信に移る。特にテレビ発の強いコンテンツを集めたポータルの活況がしばらく続くと見込む。
TVerやParaviがさらに拡大していくのか、それとも別のプラットフォームが誕生するのか。もしくは、ユーザーはYouTubeやNetflixのような海外プラットフォームに持っていかれてしまうのか。
ユーザーも広告も、結局は魅力的なコンテンツのあるプラットフォームに集まる。放送起点のコンテンツと配信起点のコンテンツがユーザーの可処分時間をどう奪い合っていくのか、動向を注視していく必要がある。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

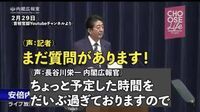





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら