もちろん、私たち在宅医療に携わる医師や看護師も最大限にサポートしますが、訪問医療や訪問看護の枠内でできる内容や滞在時間にはどうしても制約が出てきます。
保険適用にならない自費サービスを使うケースはごく稀であるものの、自費サービスとなるとどうしても費用がかさみがち。私のクリニックでも、自費の訪問看護は1時間につき8000円ほどの費用がかかります。それでも「どうしてもコンサートを見に行きたい」という患者さんのサポートとして、自費の訪問看護を使って看護師が同行したケースもありました。
家事サポートにしても、自費で家政婦さんを雇うことも経済的になかなか難しい。近くに頼れる誰かがいないことから、本当は最期まで家で過ごしたいのに、それを諦めざるをえない人もいるのです。
福祉用具のレンタルも自費で負担
まだまだ問題はあります。
体が動かなくなるにつれ、介護用ベッドや車いすなど、福祉用具のレンタルや購入も必要になってきます。これらも介護保険制度が適用にならないと、全額を自費で負担することになり、経済的な負担が大きいです。
Aさんの場合、「布団で子どもと一緒に寝たい」という希望があったので、最後のひと月だけ介護用ベッドをレンタルしましたが、それでもベッドとマットレスのレンタル料は1万円ほどかかりました。借りる期間が長ければ、それだけ費用がかさむことになります。

こうした課題を解決すべく、今、40歳未満の終末期のがん患者さんを対象に、訪問介護や福祉用具の利用料を助成し、介護保険と同程度の自己負担額で介護サービスが利用できる自治体が増えてきています。
例えば、兵庫県では2015年度から、20歳以上、40歳未満の患者さんに対し、在宅ターミナルケア(終末期医療)を支援する事業をスタート。現在、月額6万円を上限とし、利用料の9割は県と市町村が半分ずつ負担する形で助成しています。同様の助成制度が、全国各地の自治体に広がっており、なかには小児がんも対象に、20歳未満も利用できるよう間口を広げる自治体も出てきました。

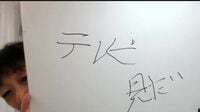





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら