小学生になり、地元の友達と遊ぶようになって「自分の方が普通ではない」と気づいた。周囲から「かわいそう」「大変だね」と、音が聞こえないことは不幸であるかのように見られるようにもなった。奥田さんは体験記に、こう書く。
――自分たち聾者が聴者中心の社会に足を踏み入れた途端、周りにとって私たちは異質な者となる。独自の方法で教育を受けたり、コミュニケーションを取ったりしている者を「障害者」と名付ける。
高校生になった奥田さんは、見識を広めながら他者と自分の違いについて 「聾者は聴者とは異なる文化を持った『少数民族』のようなもの」と考えるようになった。そして体験記では、社会に疑問を投げかける。
――もしも、聾者と聴者が生きる社会にはっきりとした境界があり、お互いに関わりを持たなかったら、社会で言われる「聴覚障害者」は、全員、自分のことを「障害者」と思わず、「聾者」という普通の人間として生きていたのではないか。
放置していたら私たちの未来は明るくない
奥田さんは今回『生贄探し 暴走する脳』(中野信子・ヤマザキマリ著、講談社+α新書)を読んで、ヒトや集団が障害者と名付けるのは「人間特有の脳のクセ」と知った。脳科学者の中野さんがこんな趣旨を説明していたからだ。
――ヒトは異なる内面、異質な外見を持った者を、執拗に排除しようとする。集団は異質な者をどうにかして排除しようと足掻く(あがく)。これは集団を作ることで生き延びてきたヒトの特有の脳のクセなのである(⋆2)。
この文章を読んで、奥田さんは「ヒトの脳はそういうものと放置していたら、私たちの未来は明るくない」と嘆く。そのうえで、こう主張する。
――社会で「多様性を認め合う」「多様性を尊重する社会の実現」というフレーズを多用するのであれば、「障害者」という言葉を考え直すことが「多様性」を維持する社会を実現する第一歩になるのではないかと強く思う。
バスケットボールや、スノーボードで雪上を滑ることが好きな奥田さんは、東京都内の大学へ進学し、今春から心理学・社会学・身体学を複合的に学ぶ。将来の夢は「障害をコンプレックスに感じる人が自信を持てるようなアドバイスをしていく仕事に就きたい」だ。
奥田さんが前述した「聾者は聴者とは異なる文化を持った『少数民族』のようなもの」と思えるようになったきっかけは、国立障害者リハビリテーションセンター学院(手話通訳学科)教員の木村晴美さん、市田泰弘さんの「ろう文化宣言」を知ったからだった。
ろう文化宣言とは、1996年、聾者の木村さんと聴者の市田さんが「聾者とは日本語とは文法が異なる日本手話を用いる者で、言語的少数者である」という趣旨を言論雑誌で発表したことをいう(⋆3)。
背景に、アメリカでは聾者の手話は英語と同列の1つの言語として認められ、聾者のコミュニティーを文化的集団と捉える視点がある。冒頭で紹介した映画でも、手話を用いた聾者の生活や聾文化がさまざまなエピソードで紹介されていた。
手話は聾者の第一言語で、手指に加えて、眉の動きや目の開き方、首の傾き方、あごの出し方なども文法の要素として表現する。近年、日本では、総理大臣や各省庁の記者会見、NHKの手話ニュース、東京2020オリンピック・パラリンピックでも手話通訳が入った。


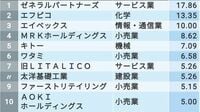




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら