松本:ええ、考え方としてはそうです。ただ、「犬と猫のどっちが好きか」というお題は、言語的にはけっこう難しい論題だと思います。中学生が知らないような難解な形容詞を使わなければならない可能性が高くなります。「給食のほうが弁当よりいいか悪いか」のほうが、意外と簡単にできるのです。ですから、ディベート活動を導入しようとする先生は、トピックを思いついたら、まず自分でやってみてほしいですね。
安河内:犬猫は一見簡単そうですが、いざ自分が英語でやるとなると、確かに思ったよりも考えてしまいますね。
松本:それに、最後は個人の趣味になってしまいがちで、そうなると議論しにくいですしね。もう少し公共性があるほうがいい。「修学旅行は海外がいい」「制服廃止」などのほうが、英語としても話しやすい。
安河内:確かに。犬猫のような主観が入りまくりのやつだと……。
松本:形容詞が難しくなってしまいますね。

安河内:授業では勝敗なんかつけないで、気軽にやったほうがいい気がしてきました。
松本:先生は議論を楽しむ雰囲気作りをすることが大切です。
安河内:けんかにならないよう、盛り上げていこうよと。What happens in the debate stays in the debate.(議論したことは、議論にとどめておく)にしようということですね。
松本:ええ。その結果としてお互いの考えが深まったり、広まったりすれば上出来です。さらに英語力もつけば最高です。
英作文の採点基準に変化が!? スペルより論理性が大事!
安河内:そのとおりですね! これからスピーキングテストが普及してくると、ディベート系の学習の注目度はもっと上がっていくと思います。
松本:ええ。ただ、今後のスピーキングテストだけでなく、既存の入試におけるライティング問題に目を向けてみても、ディベート形式のものがかなり増えてきているんですよね。昨年より今年のほうがより多くなりました。ある英文を読んでから、自分の立場を決めて書く、といった問題形式です。
安河内:入試の英作文問題には2種類ありますよね。
ひとつ目は、小難しい日本語に下線を引いて、英訳せよというものです。これも入試の世界では英作文と呼ばれます。2つ目は自由英作文と言われるものですね。こちらは「高校で制服を廃止することについてあなたはどう思いますか? 200語以内の英語で論ぜよ」というような問題です。
ここ最近は後者のタイプである、自由英作文かつ論理的に自分の意見を書かせる問題が増えてきているわけですね。
ただ増加しているのは確かですが、残念ながらひとつ目のタイプの英作文がまだ多い。特に私大は、受験者数が多いので、論理的な英作文を採点するのは大変という理由で、穴埋めタイプか、英作文自体を出題しないところが多いですね。





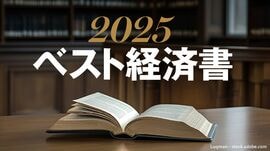


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら