松本:summaryとかsummary speechですね。
安河内:summaryは肯定側から、それとも否定側からするのですか?
松本:「ディベートは肯定で始まり肯定で終わる」というのが従来の考え方で、今でもそういった大会が多いのが事実です。でも全国高校生英語ディベート大会では、否定側のsummary speechで終わります。どちらのスピーチで終わるかは、さほど重要ではないと最近は考えられていますね。
どんなディベート大会でもまず立論があり、次にcross examinationへと進むのですが、その後は参加する学生・生徒のレベルなどによって、いろいろな進行形式が存在します。
安河内:反対尋問は誰がやるのですか?
松本:大学生の大会の場合、ほとんどが2人制ですが、全員に反対尋問の機会が与えられています。
安河内:高校、大学、または大会によってやり方がいろいろあるのですね。ディベートはガチガチのルールが存在するイメージがあったのですが、融通がかなり利くと言えそうです。
松本:そうですね。授業ではローカルルールをつくって気軽にやってほしいです。
形にとらわれない、ディベート的活動のススメ
安河内:これで初めてディベートの大枠がわかったという人も多かったと思います。進行形式に沿ってしゃべるから簡単なんだ、という点も実感してもらえたのではないでしょうか。
松本:ええ。大会となると、勝ち負けもつく競技ですが、授業で行うディベートに関しては、試合の形式にこだわらなくてもいいですよ。

安河内:勝ち負けにこだわるな、ということですね。
松本:勝敗だけじゃなくて、やり方にもとらわれすぎなくていいということです。10分程度で終わるマイクロディベートをやったっていいし、英文を読んで著者に対する質問を書くとか、著者の主張に対して反論を書くとか、critical(批評的)な考えを促進する活動を導入すれば、基本的には「ディベート的な活動」になりますから。
つまり「英文を読んで理解できました」で終わる授業ではなく、反対の立場に立って質問を考えてみるというところから始めれば、ディベートを学生時代に体験したことのない先生でも、すぐに授業で導入できると思います。「ディベート=競技」という意識が強すぎると、なかなか先に進まないんですよ。
安河内:本当ですね。怖くて手が出せないというのはあるかもしれないですから。では中学などでは、「犬と猫のどっちか好きか。その理由を述べよ」とかでもオーケーなんですね?





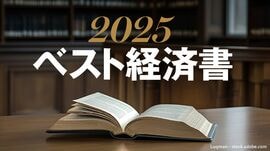


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら