ソニーがやめたAIBOと復活したaiboの決定的な差 経営陣が描くストーリーにハマるかどうかがカギ
2018年度に20年ぶりの営業最高益を出したソニーにとって、かつての輝きある「自由闊達にして愉快なる理想工場」としてのソニーブランドへの期待値を高めるためには、「遊び心」や「ユニークさの追求」のシンボルが必要だったのです。
先代のAIBOは、「ソニー冬の時代」を象徴するプロダクトでした。新生aiboは、それとは逆に、「ソニー春の時代」の期待として、経営のストーリーと整合したからこそ復活したとも言えるでしょう。
aibo開発チームであるAIロビティクスビジネスグループは、ドローンの「エアピーク」と、EVの試作車「VISION-S」の開発にも手を伸ばします。川西氏は「aiboと共通するロボティクスの要素技術は多い」と語り、aibo開発を通じて得たハードウェアとソフトウェアの融合にさらなる展開の可能性を見いだします。
ソニーはAIBOの悲劇から何を学び、どう生かしていくのか。そして、どんな尺度でもってaiboをはじめとする新規事業を再評価していくのか。その意味で、これらの新規事業は、新たなソニー経営陣の真の力量が問われるサービスになるでしょう。AIBOは果たして失敗だったのか、それはこの新たな事業次第と言えるのでしょう。
経営陣のストーリーに新規事業を乗せられるか
企業内の新規事業は、「対マーケット」における事業価値も重要ですが、「対経営陣」の事業価値も重要です。つまり、その新規事業が当該企業の経営課題に即しているか、そしてその尺度と事業が整合しているか、ということです。AIBOは「対経営陣」という側面において、その尺度にハマらなかった事業の代表例と言えるでしょう。
ここでの大きなジレンマは、どれだけ「対マーケット」でポテンシャルがあったとしても、「対経営陣」で文脈に乗らなければ新規事業として存続できないということです。その意味で、社内新規事業というのは、経営陣の一存で成否が決められてしまう極めて脆弱な存在でもあります。だからこそ、新規事業は、経営陣の描くストーリーや尺度をつねに意識し、そこに自分たちの事業がどうやって整合するのかを語らなくてはなりません。
私たちは、事業に集中するあまりに、視野をマーケットだけに集中させがちですが、その一方では会社がどのような状態であり、何を今求めているのか、ということも忘れてはならないのです。
AIBOからaiboへ。このストーリーは、事業そのものの価値もさることながら、企業の変化を理解することを伝えてくれる題材として読み取ることができるのかもしれません。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

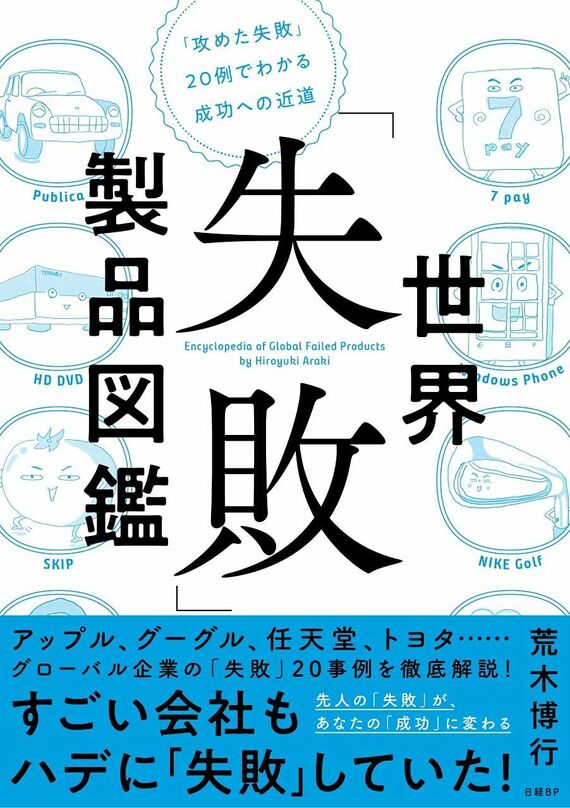

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら