ドラゴン桜が推薦「日常の価値を見直す」3冊 「タイトルしか知らない名著」の要点を紹介
『ボヴァリー夫人』ギュスターヴ・フローベール 芳川泰久(訳) 新潮文庫
「そうよ、かわいいひと。ほんとにかわいいひと……あのひと恋をしているのではないかしら?」と心にきいてみる。「だれを?……あたしを、だ!」
19世紀フランス小説を代表する、いやそれよりも小説というジャンルの「見本」を作り上げたといってもいいのがこの作品。フランスのルーアン近郊の田舎町で医者をしているシャルル・ボヴァリーは、美貌のエマを妻にめとる。
その地域では「そこそこ」の地位にあるシャルルのもとへ嫁いで、さほどの不自由もない暮らしができるのだから満足すべきところではあるはずなのに、エマの心はちっとも晴れない。夫の凡庸さや田舎の小さい世界を嫌悪して、退屈でたまらないのだ。
もともと空想癖の強かったエマはいつしか、ロマンチックな恋愛に身を浸す自分の姿を妄想するようになり、その思いが現実にまでにじみ出てくる。
出会った男性ロドルフ、次いでレオンと不貞を重ね、家庭の金銭も使い込んでしまう。
だが結局は、男性たちに都合よく利用されただけ。不都合を隠し通せなくなったエマは、服毒して死んでしまう。エマが最期を迎えるまで「いい人」であり続けたシャルルも、跡を追うように命を落とす。残された彼らの娘は、なんとか係累を頼って生き延びているようだと記され、1編は終わる。
いまならさしずめ週刊誌の記事にでもなりそうな1人の女性の顛末を、作者フローベールは、同時代の「生活の一例」として客観的に描写していく。大仰に飾り立てず、出来事と心情を淡々と言葉に落とし込んでいくことによって、リアルな読み応えを作り出しているのだ。
『ボヴァリー夫人』まとめ
起こった出来事だけを追えば、どこにでもありそうな陳腐さ。それが時代を超えて読み継がれるのは、描き出しているのが時代の風俗だけではなく、人の内面と感情をも含んでいるからだ。これは出来事の新奇さで読ませるのではなく、内面の動きだけで自律している小説だ。
人の感情はどんなときにどう動き、いかにすれば満足を得るのか、名作小説からよくよく読み取れ。人の世のすべての課題もその解決策も、人の感情に基づいて生まれているのだから。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

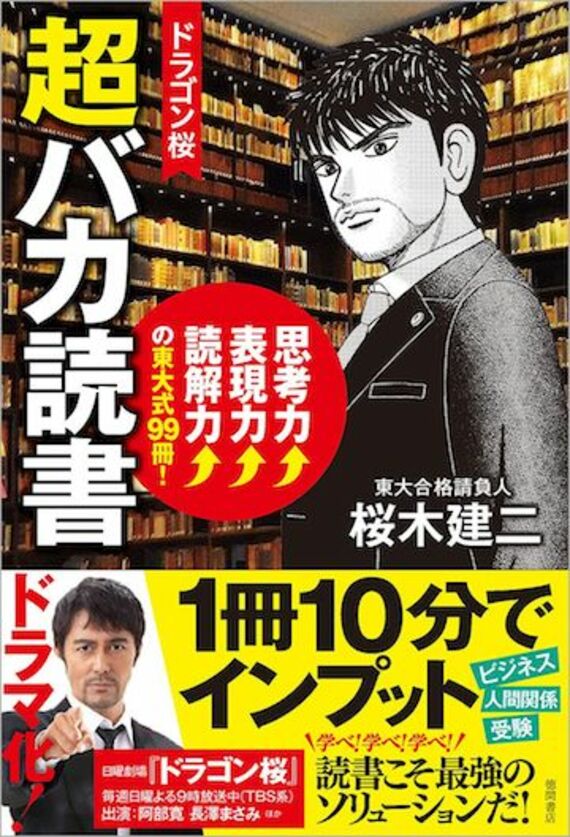
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら