山崎正和が創りあげた「知の交差点」の磁場 開高健、高坂正堯、梅棹忠夫、小松左京も結集
文化財団の設立の1カ月前の1979年1月、社長の佐治敬三を発行人としてサントリー広報部から『サントリークォータリー』が創刊された。私は広報も編集も兼務。内容は、文化全般を視野に入れたが、一方で文化財団の動きに歩調をあわせ、編集長インタビューなどでも、山崎正和に登場していただいた。
さらに経営方針の一環でサントリーは、2年後の1981年8月、TBSブリタニカを自社の傘下とした。当時、資本金10億円、社員数200人余の百科事典と教養書に強い準大手出版社だった。急転直下、私は同社編集担当役員として出向が決まる。出版局長兼務だった。
なぜ、こんなことを書いているのか。1986年6月、サントリー文化財団の『アステイオン』創刊号が、TBSブリタニカ出版局で産声を上げたからだ。誌名は山崎正和がギリシャ語から命名。編集部は、出版局に置かれ、山崎正和、粕谷一希、高坂正堯というそうそうたる人々が、東京は三番町のオフィスに出入するようになった。開高健は少し遅れて同社の編集顧問に就任し、『サントリークォータリー』の編集部はすでに出版局に置かれていた。
創刊時、『アステイオン』は統括が山崎正和、編集長に粕谷一希、編集部員として出版局の編集者も兼任した。さらに山崎の意向で、木挽社(こびきしゃ)の藤田三男、久米勲らも編集に参加。『アステイオン』の編集会議は、出版局の会議室で開かれ、私も出席。編集用ワーキングテーブルは、私のデスクの隣だった。出版局にはサロン的雰囲気があった。
藤田は、河出書房新社に在職中、山崎正和が論壇デビューの頃の編集担当者で、本書では『世阿弥』(1964年)で岸田國士演劇賞を受賞した後の『劇的なる精神』(1966年)、『このアメリカ』(1967年)を上梓する前後を克明に回顧していて飽きさせない。
その2年前には江藤淳が『アメリカと私』を朝日新聞社から出しており、山崎の『このアメリカ』は好対照だった。2つの個性がくっきりと表れていて、その点も話題になり、私には懐かしい1冊だ。
ジャーナリズムへの根本的な関心
現在、『アステイオン』(発行=CCCメディアハウス)は、論壇時評にも取り上げられるクオリティー・マガジンである。元をたどれば山崎に行き着くが、むろん山崎の活動はサントリー文化財団だけにとどまらない。幅の広いことでも知られており、実は次のエピソードはいささか脇道めくが、あえて山崎の知られざる一面をたどる意味で書いておきたい。
2000年3月、私はサントリーを退職した。前年5月、神奈川近代文学館で開催された「開高健回顧展」会場で、病を押して見にこられた佐治敬三会長とけい子夫人に会う。日曜日だった。そのとき「母校から招かれたのなら行くべきやなァ」と一言つぶやかれた。背中を佐治に押された私はその年の秋、早稲田大学顧問と非常勤講師になった。
もっとも、その任に私がつくというのが主目的ではなく、大学は新事業「石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞」を運営する人間を探していたのだ。この賞は新聞、テレビ、書籍、ネットなどあらゆるメディアを対象に優れたジャーナリストを3部門にわたり顕彰する年度賞だった。奥島孝康総長と渡辺重範副総長に会って、私はジャーナリズム大賞事務局長に就任した。

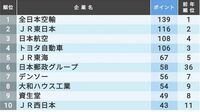






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら