ハリウッドから「中国が悪者」の映画が消えた訳 逆にどんどん増える「中国人が大活躍」の映画
2018年、カンヌ国際映画祭最高賞パルムドールを受賞した『万引き家族』のテーマはInvisible people(社会から隔絶・孤立した人々)、2019年、アカデミー賞作品賞受賞作『グリーンブック』のテーマは、Diversity(多様性、差別)だ。そして、世界中で大きな話題となった2020年、アカデミー賞作品賞に輝いた韓国映画『パラサイト 半地下の家族』、そのテーマはDisparity(格差)である。
中国からは、このどれも生まれることはない。
映画は、基本的に、何らかの社会的制約や障害との葛藤と、その克服がテーマなのだ。ところが中国では、葛藤を描かれても、それを克服されても困るのである。ほとんどのことは統制のもとにNGだ。
しかも、統制を破ることは、中国では想像もつかないほど大きなリスクとなる。日本で1980年当時、『四畳半襖の下張』事件(文書のわいせつ性の判断基準が争われた刑事事件)で、被告の野坂昭如氏は有罪となった。彼は「その後」も事あるごとにこのときの判決を批判し、笑い飛ばしていた。そして実際に、この事件は笑い話の種になった。
これが中国だったら笑い話では済まない。野坂昭如氏に「その後」などなかったはずだ。
このような条件下では、すでに検閲を通過して安全なもの、つまり過去に前例があるものを、手を替え品を替えて作り直していくしか安全な道はない。
自由な発想と自由な表現は、「創作」に欠かせない絶対の要素なのである。中身が粉飾されたり、歪曲されていたら、コンテンツとしての価値は失われてしまう。
「創出力」で圧倒できたら中国は変わるかもしれない
中国が映画をはじめとしたコンテンツの消費国として巨大化していくことに間違いはないが、コンテンツ開発国・供給国として世界のエンターテインメント業界に君臨することは、当面ないだろう。思いのままに、多様なオリジナルを送り出す自由がないからだ。
ファッションブランドでも状況は同じだ。いま、世界中の高級ブランドを買いあさっているのは中国だ。中国が世界でいちばんのブランド購入国であることは間違いない。
しかし、だからといって中国をブランド大国とはいわないし、ブランド強国と呼ぶこともない。自らブランドを創出し、ブランドで外貨を稼いでいるわけではないからだ。「模倣ブランド大国」とは呼ばれているが。
映画をはじめエンターテインメントの分野で、中国が世界をリードすることはない。
しかし、中国がすごいのは、前にいる者を一気に抜き去るパワーだ。「勢い」はしばらく止まらない。
もし、エンターテインメントの世界で、中国がコンテンツの「創出力」で他国を圧倒する時代が到来したら、そのときの中国は、世界中に愛される国になっているだろう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

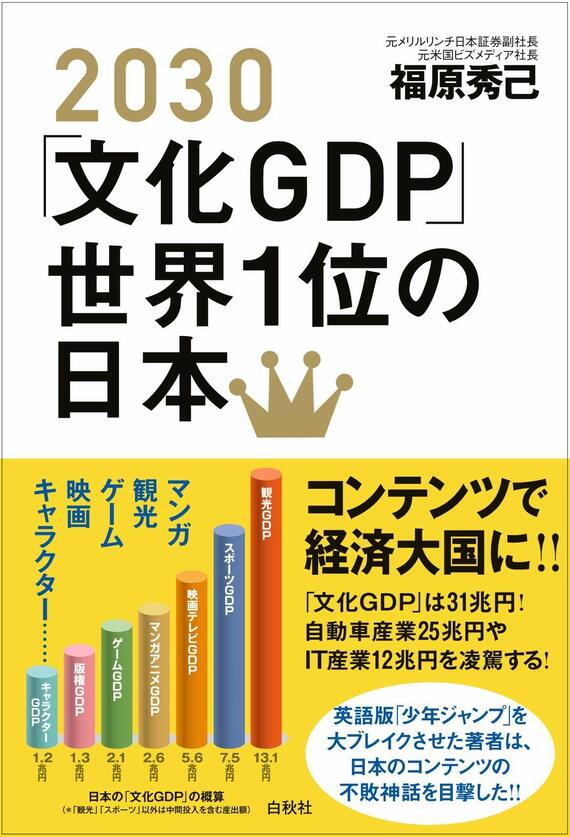































無料会員登録はこちら
ログインはこちら