子どもにあれこれ言う親が的外れでしかない訳 アイコンタクトひとつでできる究極の子育て
以上の専門家の意見を煎じ詰めれば、自己肯定感を育むうえでも非認知能力を伸ばすための大原則は、親が先回りして子どもにあれやこれやを与えることよりも、子どもをできるだけ自由に遊ばせて、その様子をつねによく見て子どもが発する興味関心のサインを見逃さないことだと言えます。
アイコンタクトを返すだけでもいい
幼児であれ思春期の子どもであれ、「いま、僕頑張ったよ。見てた?」とか「やった! わたし、すごいでしょ?」という意味で、親をチラッと見ることがありますよね。それがサインです。そのときに「うん、見てたよ」「すごいじゃん!」とアイコンタクトを返すだけでもいいのです。
それだけで子どもは勇気づけられ、励まされます。「お父さん、お母さんはちゃんと自分のことを見ていてくれる」と安心します。
逆に、スマホをのぞき込んで他人のSNSに「いいね!」なんてしていたがために、子どもがせっかく発したサインを見逃すようなことが連続すると、子どもはだんだんとやる気を失っていきます。「どうせ……」が口癖になっていくのです。
親が子どものためにあれこれ手を出したり口を出したりするのは最低限にとどめるべきだと、わたし自身は思っています。でも、子どもに背を向けてなにもしないほうがいいといっているわけではありません。子どものありのままの姿、振る舞いを近くで見守り、子どもが「いま、見てた?」とこちらを見たときにはできるだけそれに気づいてあげて、目の動きひとつでいいので「見てたよ!」というサインを送り返してあげてほしいのです。
それさえできれば、余計な心配などしなくても、子どもは勝手にぐんぐん伸びていくはずです。それが、さまざまな専門家の話を聞き、さまざまな教育の現場を見てきたわたしの、現時点での結論です。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

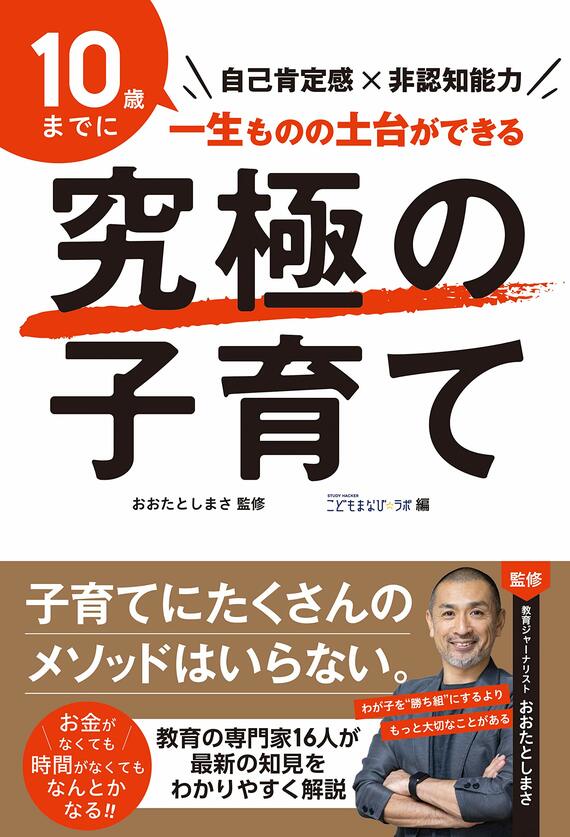






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら