脳機能の低下を防ぐには「手書き」が有効だ 「あれなんだっけ」が増えていませんか?
本を読んだ、あるいは映画やDVDを見たあとにA4用紙1枚を使うということがルールです。書くこと自体がアウトプットになりますが、あとから見返せるように、バインダーにまとめておくのがいいでしょう。
私が書く内容は以下の事柄です。
●(本の場合は)タイトル、著者名、出版社名
●仕事に役立つと思った情報
●印象に残ったフレーズ
●新鮮だと感じた表現
●読みながら浮かんだ疑問
これらの項目を箇条書きにしてまとめてみましょう。
アウトプットすることで、ワーキングメモリを解放する
時間がないときは、
●(本の場合は)タイトル、著者名、出版社名
この2つだけをメモしておき、あとでほかの項目を書き足します。
「内容をまとめる」と聞くと、学生時代の読書感想文のように、長い文章を書かなければならないと身構えてしまう人がいますが、このトレーニングでは、「箇条書き」にまとめることがポイントです。箇条書きにまとめることは、読解力や文脈を捉える能力を高めます。
読書をし、本の内容を箇条書きにまとめることは、ワーキングメモリを解放することにつながります。つまり、アウトプットしたことで、読んでインプットした知識を脳は忘れてもいいと判断するので、ほかのことを覚えるために、ワーキングメモリの機能をフルに使うことができるというわけです。
手書き習慣がなくなっているなと感じたら、1度トライしてみてください。人生100年時代、手で文字を書き続ければいくつになっても脳が活性化します。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

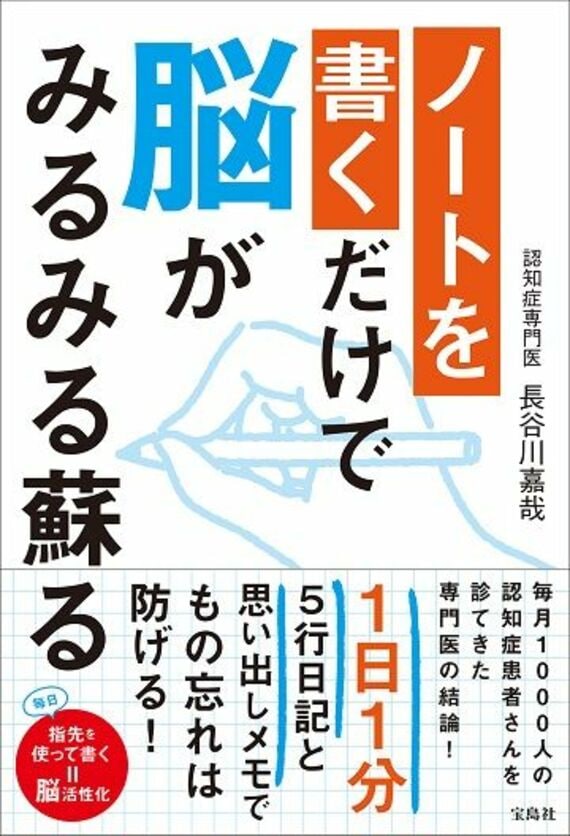
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら