不倫を「モラル」で断罪しないフランス人心理 「困ったこと」だけれど悪くはないという認識
科学の発展を背景として、理性を人間にとって普遍的なものとする啓蒙思想、そしてそれを思想的基盤として起きたフランス革命の結果、現代の民主主義の基盤となる一文、「人間は生まれながらにして自由で権利において平等」を含む全17条の人権宣言が採択され、共和制樹立が宣言された。「自由」は、時代のキーワードとなった。
しかし、宗教的モラルが紙くず同然の価値しか持たなくなったとき、「私の自由」をとことん実現することで、「他人の自由」が侵害されることはないだろうか? 神を否定するジュリエットと「犯罪友の会」の仲間たちが「私の自由」「私の幸福」「私の快楽」のみを追求する『悪徳の栄え』の世界では、弱者はもはや強者の欲望を満たす「快楽のための道具」でしかなく、彼らが苦しむ声はまったくと言っていいほど聞こえてこない。
いや、理性こそが宗教的モラルにとって代わるというのならば、理性が暴走したり暴力を犯したりすることはないのか?
ジュリエットは、まさに宗教とそれにまつわる迷信や感情、悔恨や道徳、慈悲、愛情といった理性にかなわないものをばかばかしいと考える理性万能主義者だ。しかし、非合理なものをすべて排除する社会が、人間にとって本当に幸せな社会であるかどうかは、甚だ疑問だ。
サドの作品は、劣悪人種と見なされたユダヤ人やホモセクシャル、ロマ族がナチス・ドイツによって大量虐殺された第2次世界大戦や、効率第一主義の社会に適応できない者は切り捨てられる現代のネオリベラリズムを予告し、自由とその負の側面、人間の理性とその限界について、今もなお私たちに切実に問いかけるものだ(*7)。
近代から現代を通じて、フランスでは「自由とは何か」が文学、哲学、政治、経済、風紀といったさまざまな分野で議論されてきた。その結果、恋愛とセックスの自由は、キリスト教が国教となった5世紀末から20世紀初頭まで、つまり約1400年にわたるキリスト教との熾烈な戦いの末に獲得した、かけがえのないものとして認識されている。
恋愛とセックスの自由にモラルが介入する余地は?
だから、フランスの人々はそこへ安易にモラルが介入することを嫌い、それゆえ他国の人々から「フランス人はアンモラルだから」と誤解を受けるのだろう。
しかし、その根底には、フランス革命後200年をかけて練り上げられた、「自由=やりたい放題」ではなく、「自由=他者への責任や連帯の義務を伴う」という考えを土台にした、民主主義的な枠組みがあるように思える。
それが、「成人で相手が合意の上であれば、どんな関係もOK」という考えである。この条件さえクリアすれば、恋愛は容赦なくライバルを蹴散らすシビアな自由競争と化す。「奪った者勝ち」の世界である。
目下不倫中の同僚、ロランスは言う。
「不倫を悪いことだと思っているわけではないの。ただ、堂々とできないこと、コソコソしなくてはならないことには困ってる」
そう。
「困ったこと」ではあるけれども、悪くはない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

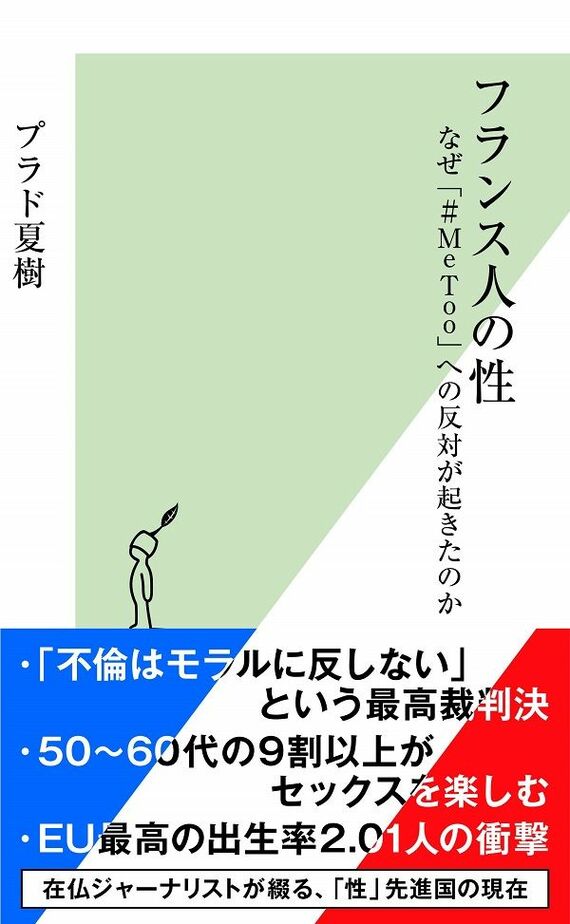

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら