こうした「文化」の下では、人は自然に勤勉になり、絶えず確認するようになり、相手の言葉を信じないようになり……そして、相手は莫大な失敗を犯してもおいそれとは謝りませんから(先の銀行の失敗を追及すると「10年に1度の失敗です」と言ってハハハと笑うだけでした)、精神の健康を保つには、「まさに詰め寄って相手を責める」という(少なくとも)演技が必要なのです。
その場合、特に大切なことは、絶対に逃げてはならないということです。どんな小さなことでも相手の不正を見逃さないこと、少なくとも1度ははっきりと「あなたは間違っています、なぜなら……」と、言葉できちんと抗議することです。たとえ相手がそれを認めなくても、謝ることがなくても、これを続けていれば、精神の健康が決定的にむしばまれることはないでしょう。
知り合いの音楽女学生が、教授がしばしば差別語を使い、自分より西洋人をいつも優遇し、憤懣やる方なかったが、じっと我慢しているうちに精神の均衡が保てなくなった、大学に行くことができなくなった、と言っていたのをよく憶えています(その後どうしたか知りませんが)。わが国ではある程度通じる「丸く収める」とか、「いつかわかってくれる」という悠長な考えがまったく通じない文化ですから、次々に降りかかる不正な仕打ちを我慢していると――人間とはそういうものだと思うのです――他人が怖くなり、自己嫌悪も高まり、果ては生きる気力もなくなります。そうならないためには、「強く」そして(あえて言えば)「悪く」ならなければならないのです。
私は「悪く」なる才能があった
今から考えても不思議な気がするのですが、私はウィーンに適応する才能がありました。つまり、特に「悪く」なる才能がありました。日々刻々、さまざまな理不尽な仕打ちと戦っているうちに、私はしだいにドイツ人のようになっていったのです。そして、挙げ句の果ては、明らかに自分が悪くても、絶対に謝らずに相手を攻めまくり、不利と思ったらあっという間に態度を変え、弱そうな相手には大声を上げ、強そうな相手には一時退却して対策を練る……といったドイツ人なら「普通にすること」が苦もなくできるようになりました。そして、4年半におよぶウィーン時代を乗り切ったのです。
私はもともと十分、下品であり、悪に適応する能力があったので、そうした才能が見事にウィーンで開花したのでしょうが、自分のワルさズルさにあきれかえりながらも、ウィーンでのこの変身は、自分にとって心から「よかった」と思っています。なぜなら、これによって私はドクター論文の完成という自分の目的を達せたからでもありますが、もっと大きな理由として、「自分は十分アクなのだ、ズルなのだ」という自覚を持てたからです。その後、日本でも私を採用してくれた教授との壮絶な戦い(いじめ)をはじめとして、闘争は絶え間なかったのですが、どんなに相手から卑劣な仕打ちを受けても、「俺も同じように、いや相手以上に卑劣なのだ」という声が体内から響いてきて、相手を根底では許せるのです。


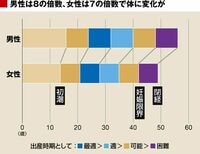





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら